
https://kinomachina.blog
感化されて、近くの店でジョージアのサペラヴィを買ってきて、ネットで調べたレシピをもとに、なんちゃってチジビジを作った(トマトの量が少ない)。
ちなみに映画の最後に出てくる教会は6世紀に建てられたジワリ修道院らしい。


感化されて、近くの店でジョージアのサペラヴィを買ってきて、ネットで調べたレシピをもとに、なんちゃってチジビジを作った(トマトの量が少ない)。
ちなみに映画の最後に出てくる教会は6世紀に建てられたジワリ修道院らしい。


UNEXTが正しいというわけではなくて、手もとにあったからなんですが、先年出た日本版の4Kではどうなっているんだろう。


UNEXTが正しいというわけではなくて、手もとにあったからなんですが、先年出た日本版の4Kではどうなっているんだろう。
左がLumière Beneluxが「4Kリストア版」として公開しているトレイラーから。右はUNEXTの同じシーン。この色の違いはなぜ?


左がLumière Beneluxが「4Kリストア版」として公開しているトレイラーから。右はUNEXTの同じシーン。この色の違いはなぜ?






SF映画もフィルム・ノワールも後世の概念で、この時代には「シチュエーションが大袈裟で、登場人物は理解しやすく、観客が感情的に揺さぶられる」くらいの意味合いの「Melodrama」に該当する、と考えられていたのでしょう。



SF映画もフィルム・ノワールも後世の概念で、この時代には「シチュエーションが大袈裟で、登場人物は理解しやすく、観客が感情的に揺さぶられる」くらいの意味合いの「Melodrama」に該当する、と考えられていたのでしょう。
例えば、これは1949年の業界誌ですが、製作予定の映画リストのなかに『月世界征服(Destination Moon)』と『海底二万哩(20000 Leagues Under the Sea)』があります。どちらも「Melodrama」に分類されているんです。まだ「サイエンス・フィクション映画」というジャンルの概念が浸透していなかったからなんだと思います。




例えば、これは1949年の業界誌ですが、製作予定の映画リストのなかに『月世界征服(Destination Moon)』と『海底二万哩(20000 Leagues Under the Sea)』があります。どちらも「Melodrama」に分類されているんです。まだ「サイエンス・フィクション映画」というジャンルの概念が浸透していなかったからなんだと思います。



kims-video.com

kims-video.com









トレンチコートは基本、ラグラン・スリーブなんですが、ポルコのトレンチコートは珍しくセットイン・スリーブなんですよね。実は『カサブランカ』のハンフリー・ボガートのトレンチコートもセットイン・スリーブなんです。おそらく、キャラクターデザインの時に『カサブランカ』を参考にしていて、ちょっと珍しいセットイン・スリーブになったのではないでしょうか。


トレンチコートは基本、ラグラン・スリーブなんですが、ポルコのトレンチコートは珍しくセットイン・スリーブなんですよね。実は『カサブランカ』のハンフリー・ボガートのトレンチコートもセットイン・スリーブなんです。おそらく、キャラクターデザインの時に『カサブランカ』を参考にしていて、ちょっと珍しいセットイン・スリーブになったのではないでしょうか。

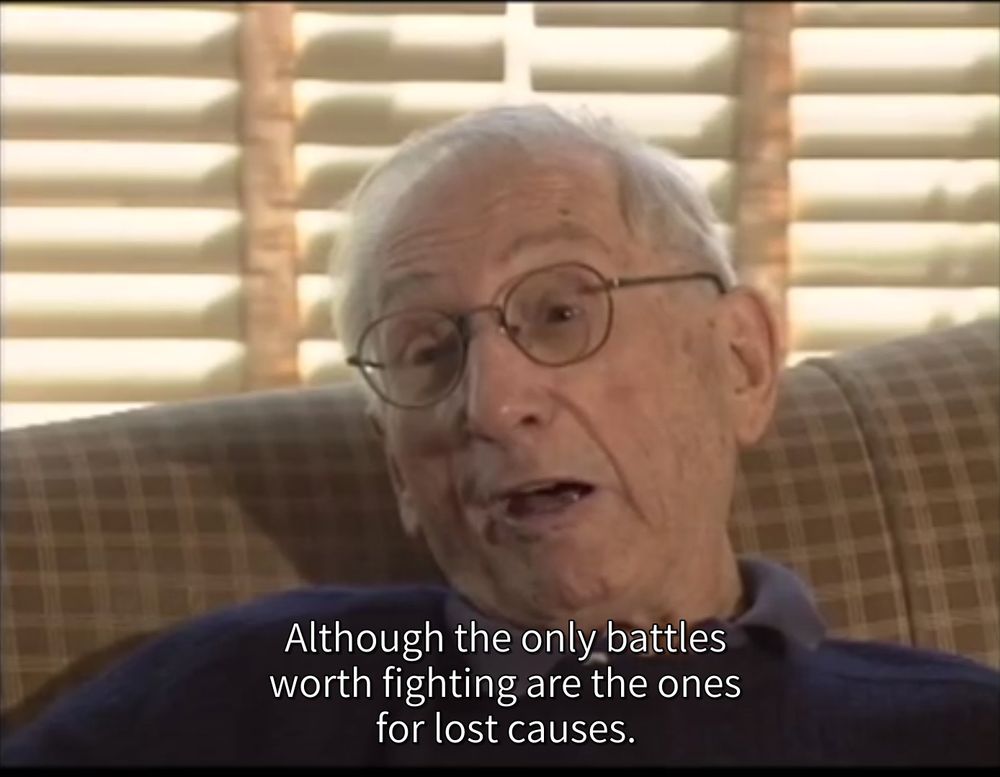

この第2巻で取り上げた10本の映画を38秒で紹介します。
この印象的な映像を撮った撮影監督たちは
らせん階段(ニコラス・ムスラカ)
ギルダ(ルドルフ・マテ)
暁の死線(ニコラス・ムスラカ)
青い戦慄(ライオネル・リンドン)
記憶の代償(ノーバート・ブロディン)
黒い天使(ポール・イヴァノ)
殺人者(エルウッド・ブレデル)
真昼の暴動(ウィリアム・H・ダニエルズ)
十字砲火(J・ロイ・ハント)
死の接吻(ノーバート・ブロディン)
です。
この第2巻で取り上げた10本の映画を38秒で紹介します。
この印象的な映像を撮った撮影監督たちは
らせん階段(ニコラス・ムスラカ)
ギルダ(ルドルフ・マテ)
暁の死線(ニコラス・ムスラカ)
青い戦慄(ライオネル・リンドン)
記憶の代償(ノーバート・ブロディン)
黒い天使(ポール・イヴァノ)
殺人者(エルウッド・ブレデル)
真昼の暴動(ウィリアム・H・ダニエルズ)
十字砲火(J・ロイ・ハント)
死の接吻(ノーバート・ブロディン)
です。

