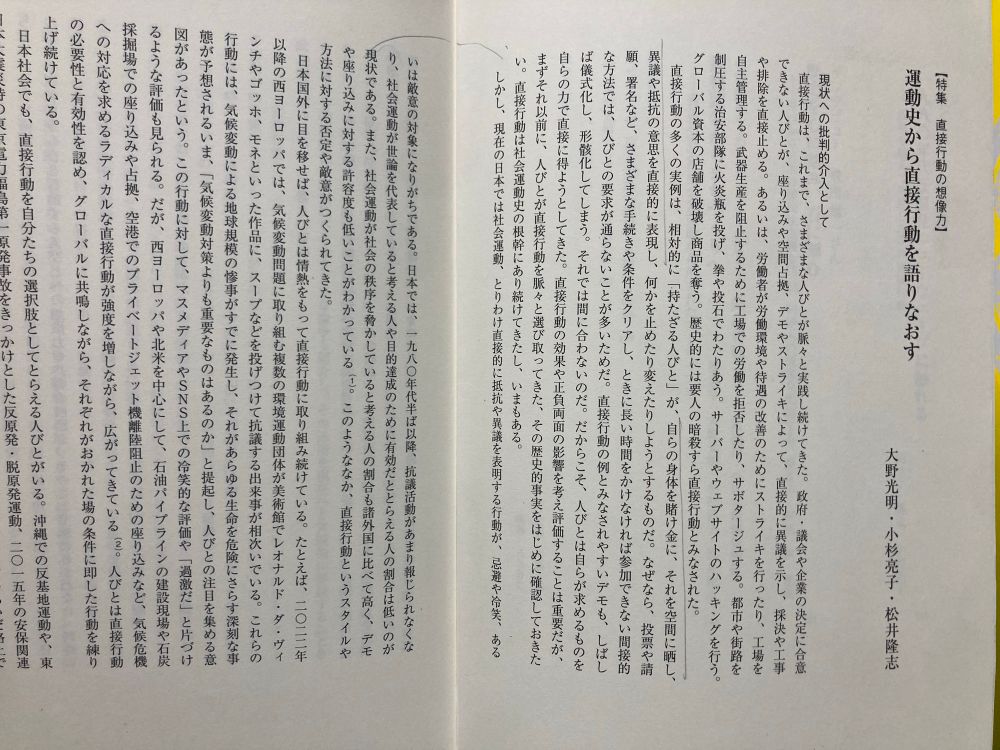こういうマップを目次のそばに添えてるんだけど、こういうのはツッコミながら眺めさせる力があるから、フックとしても悪くないんだろうね。このマップだけで、わりと従来のまとめから差異化できてる。
右半分が特に「現状」という強調だろうなあ。

こういうマップを目次のそばに添えてるんだけど、こういうのはツッコミながら眺めさせる力があるから、フックとしても悪くないんだろうね。このマップだけで、わりと従来のまとめから差異化できてる。
右半分が特に「現状」という強調だろうなあ。




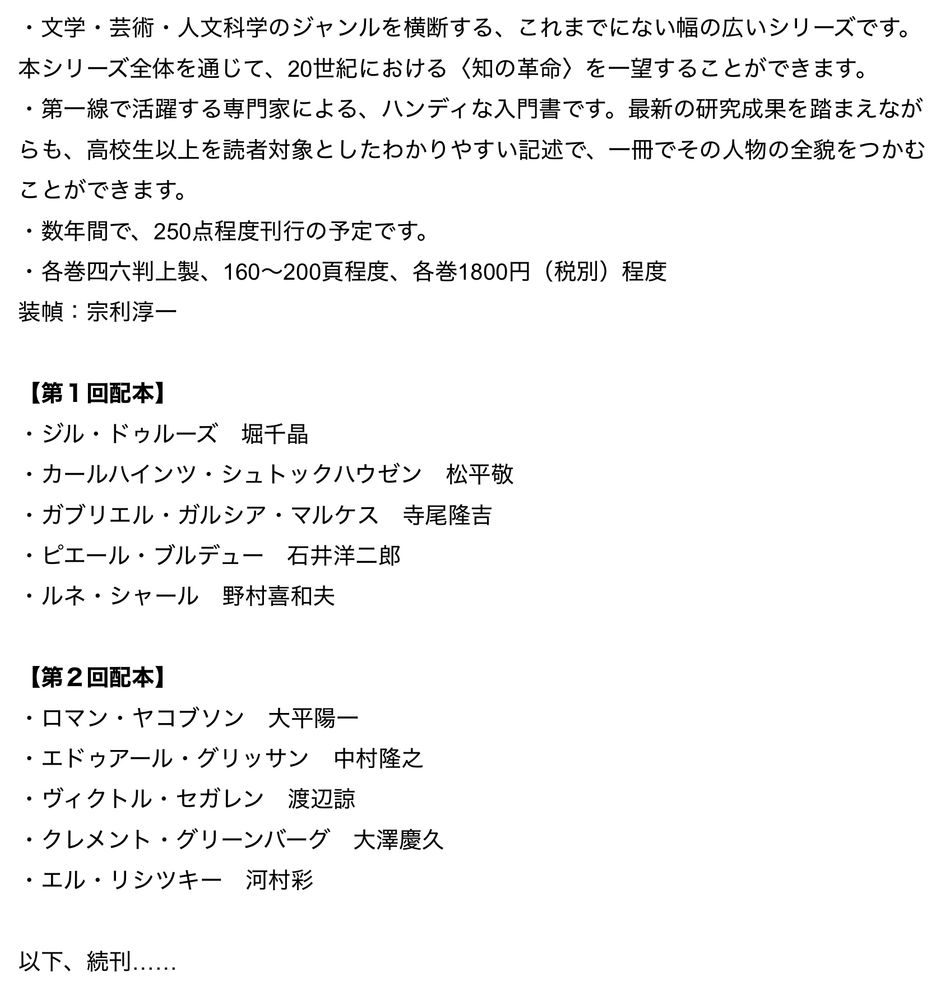
自分が「最近のマンガは貧困や荒廃の要素が増えてきたにぇい」とか思ってるのと、この棚のカラーがあまりに重なるような気がした。にゃるらも案外エンカレッジキャラとして機能してるのかもね。で、SNSでは大学生がその文脈を気付けない、自分の性欲と学歴ベースのプライドで見てしまう、というのが起きそう

自分が「最近のマンガは貧困や荒廃の要素が増えてきたにぇい」とか思ってるのと、この棚のカラーがあまりに重なるような気がした。にゃるらも案外エンカレッジキャラとして機能してるのかもね。で、SNSでは大学生がその文脈を気付けない、自分の性欲と学歴ベースのプライドで見てしまう、というのが起きそう



(『ブックライフ自由自在』)


(『ブックライフ自由自在』)
認知地図のこの箇所を、「人文と社会科学の知性がないアホ」扱いって…スーパーだめじゃん。
ポストモダン時代におけるメタフィクションがいかに現状を映し出してるかを示唆してる箇所だよ。ジェイムソンの映画論でも続行されてる論点だし、限界はあるいが興味深い現れ、の扱いなのでは。


認知地図のこの箇所を、「人文と社会科学の知性がないアホ」扱いって…スーパーだめじゃん。
ポストモダン時代におけるメタフィクションがいかに現状を映し出してるかを示唆してる箇所だよ。ジェイムソンの映画論でも続行されてる論点だし、限界はあるいが興味深い現れ、の扱いなのでは。
やっぱ面白いな。ジェイムソンを読む旅に出よう。




やっぱ面白いな。ジェイムソンを読む旅に出よう。
何冊か持ってるし、すでにちくま学芸に入ったものもあるが…。



何冊か持ってるし、すでにちくま学芸に入ったものもあるが…。



(エレン・モアズ『女性と文学』研究社)



(エレン・モアズ『女性と文学』研究社)


鷲谷花「恐怖のフェミニズム」、『姫とホモソーシャル』青土社、2022年。




鷲谷花「恐怖のフェミニズム」、『姫とホモソーシャル』青土社、2022年。
人型のあとで、「魚型もいいじゃん」に戻してこそ多様性に見えるので、そこは「親密になったら人型で固定」ではなく、異種と人型の往復であってほしかった。

人型のあとで、「魚型もいいじゃん」に戻してこそ多様性に見えるので、そこは「親密になったら人型で固定」ではなく、異種と人型の往復であってほしかった。


2000年以後のホラー年表

2000年以後のホラー年表
今作と『近畿地方』、両方ともメディアコメンタリーとか芸能界の隙間を扱う要素がある。場末メディアとか場末ステージへの自己言及みたいな要素。そういうメディアの世俗的生態、つまりメディアごとの序列や芸能人としての地位、脱落といった気配ががかなり入ってるのが、かつてのJホラーイメージとの差異なのだろう。
その世俗性、地位の気配は、言い換えると、貧乏臭さをうまくチューニングして見せているとも言えるが。

今作と『近畿地方』、両方ともメディアコメンタリーとか芸能界の隙間を扱う要素がある。場末メディアとか場末ステージへの自己言及みたいな要素。そういうメディアの世俗的生態、つまりメディアごとの序列や芸能人としての地位、脱落といった気配ががかなり入ってるのが、かつてのJホラーイメージとの差異なのだろう。
その世俗性、地位の気配は、言い換えると、貧乏臭さをうまくチューニングして見せているとも言えるが。
『ペルソナ4』2話のこの箇所おもろい。これ『同級生』(elf, 1992)の複数ルート同時攻略可能側面を、マンガに取り込んでいた『神のみぞ知るセカイ』をさらに取り込んで、テレビチャンネルのように自分を見立てて、タイムスケジュールを組む絵面なんだな。




『ペルソナ4』2話のこの箇所おもろい。これ『同級生』(elf, 1992)の複数ルート同時攻略可能側面を、マンガに取り込んでいた『神のみぞ知るセカイ』をさらに取り込んで、テレビチャンネルのように自分を見立てて、タイムスケジュールを組む絵面なんだな。
序盤は畳み掛けるモキュメンタリー的メタメディア性・途中からは原作改変性が見どころ。ラストは完全に白石味付けなので原作の原型はほぼなし。でも原作者も「白石作品ならこれでいいっしょ」とノリノリでやってそう。
最初のモキュメンタリー性というか、メディアの入れ子感が特に目を引く。いくらでもスマホや画面から身を引き離せられる動画を、「映画館で強制試聴させる」みたいな場所の交換があるのと、映画のイメージの秩序が作り上げるものが、「市街地俯瞰ショット」と「地下室=アーカイブ」のあいだみたいな感じを受ける。そうした取り組みが一番面白い。

序盤は畳み掛けるモキュメンタリー的メタメディア性・途中からは原作改変性が見どころ。ラストは完全に白石味付けなので原作の原型はほぼなし。でも原作者も「白石作品ならこれでいいっしょ」とノリノリでやってそう。
最初のモキュメンタリー性というか、メディアの入れ子感が特に目を引く。いくらでもスマホや画面から身を引き離せられる動画を、「映画館で強制試聴させる」みたいな場所の交換があるのと、映画のイメージの秩序が作り上げるものが、「市街地俯瞰ショット」と「地下室=アーカイブ」のあいだみたいな感じを受ける。そうした取り組みが一番面白い。
(陶山幾朗『「現代思潮社」という閃光』)

(陶山幾朗『「現代思潮社」という閃光』)