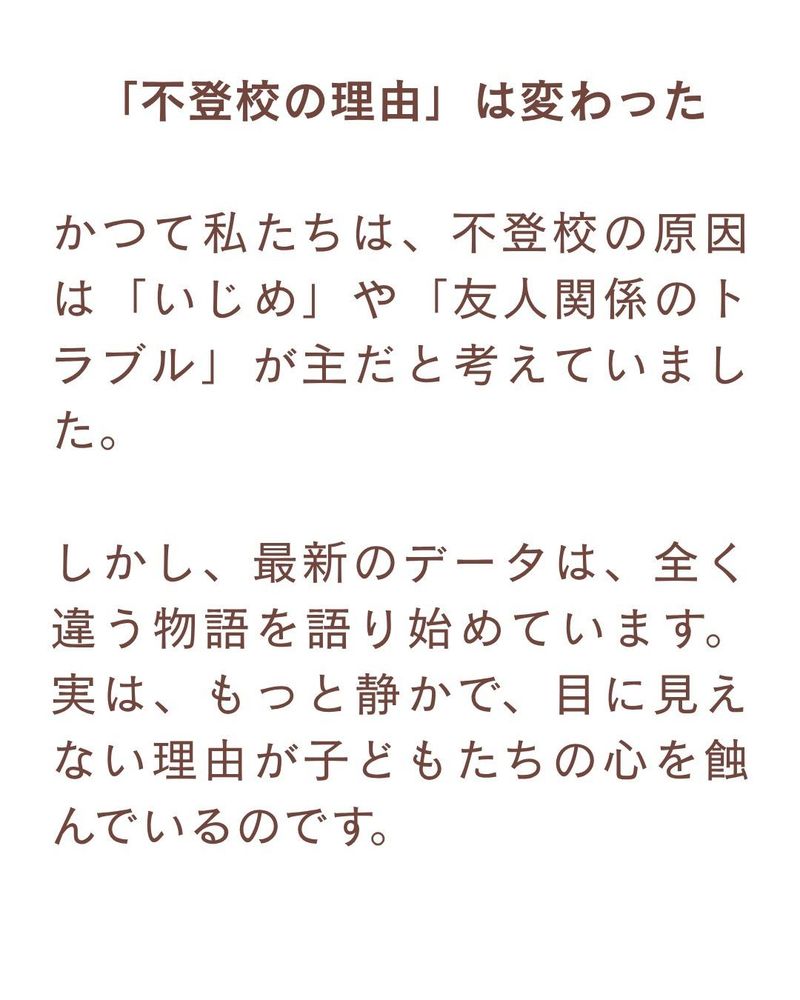親子支援歴20年×メンタルサポーター
親の心を整え、お子さんの見方を変える実践型サポート
🎁 10の実践ツール+5日間で親子関係が整う無料チャレンジ
📩 LINEから今すぐ無料受け取り
公式ライン
https://lin.ee/NKkcCNv
不登校の半数以上は無気力や不安が背景で、親が無理に連れ出そうとすると、体が震えるほどのつらさを抱える場合もあるようです。
原因が見えなくても甘えではなく、お子さん本人の深い困難や感覚が関係していることを考えて、なるべく寄り添い支える視点も持つことが大切と感じます…!
不登校の半数以上は無気力や不安が背景で、親が無理に連れ出そうとすると、体が震えるほどのつらさを抱える場合もあるようです。
原因が見えなくても甘えではなく、お子さん本人の深い困難や感覚が関係していることを考えて、なるべく寄り添い支える視点も持つことが大切と感じます…!
保護者の9割が学校から説明を受けておらず、制度は事実上眠ったままのようです。子どもに合った学び方を選べるはずなのに、学校側の都合で機会が奪われている現状は残念ですが、その背景に何か問題がないかもよう分析ですね(先生の忙しさ、人員不足なのか、学校への周知の問題なのか)
制度を知るだけで救われる子は多いと考えると、もっと広まってほしいと思います。
保護者の9割が学校から説明を受けておらず、制度は事実上眠ったままのようです。子どもに合った学び方を選べるはずなのに、学校側の都合で機会が奪われている現状は残念ですが、その背景に何か問題がないかもよう分析ですね(先生の忙しさ、人員不足なのか、学校への周知の問題なのか)
制度を知るだけで救われる子は多いと考えると、もっと広まってほしいと思います。
不登校の子や家庭、フリースクールから感謝が寄せられ、当初から「学校に行かなくても学べる環境を作りたい」という思いで続けてきたといいます。
学びの機会が「学校に行ける子だけの特権」にならない状況を、個人の努力でここまで広げていることは大きく、実際に子どもを救っているのはこうした民間の柔軟な取り組みだと感じますね…!
不登校の子や家庭、フリースクールから感謝が寄せられ、当初から「学校に行かなくても学べる環境を作りたい」という思いで続けてきたといいます。
学びの機会が「学校に行ける子だけの特権」にならない状況を、個人の努力でここまで広げていることは大きく、実際に子どもを救っているのはこうした民間の柔軟な取り組みだと感じますね…!
メラトニン分泌の遅れで夜眠れず、わずかな刺激で眠りが浅くなり、朝の一連の行動を組み立てること自体が負担になる。それには、小さな成功体験を積み、環境の方を自分に合わせていく工夫が重要と言われています。
不登校や遅刻に悩む当事者・親が「やる気の問題」にされがちな現状は辛いですね。苦手の背景に“構造”があると知るだけで、自己否定が和らぎ、支援の方向性も見えやすくなるのではないでしょうか。
news.yahoo.co.jp/articles/cb8...

メラトニン分泌の遅れで夜眠れず、わずかな刺激で眠りが浅くなり、朝の一連の行動を組み立てること自体が負担になる。それには、小さな成功体験を積み、環境の方を自分に合わせていく工夫が重要と言われています。
不登校や遅刻に悩む当事者・親が「やる気の問題」にされがちな現状は辛いですね。苦手の背景に“構造”があると知るだけで、自己否定が和らぎ、支援の方向性も見えやすくなるのではないでしょうか。
news.yahoo.co.jp/articles/cb8...
背景には「景気の変動」「家庭環境の不安定化」「子どものストレス発散の場の欠如」という三つの要因が指摘されています。経済格差が親のストレスや家庭不和を生み、それが子どもに連鎖していると。
社会が「成果」や「競争」に偏るほど、子どもたちの心の安全地帯が失われていきます。校内暴力は「問題行動」というより、社会全体のひずみが写した姿なのかもしれないですね…。
news.yahoo.co.jp/articles/15b...

背景には「景気の変動」「家庭環境の不安定化」「子どものストレス発散の場の欠如」という三つの要因が指摘されています。経済格差が親のストレスや家庭不和を生み、それが子どもに連鎖していると。
社会が「成果」や「競争」に偏るほど、子どもたちの心の安全地帯が失われていきます。校内暴力は「問題行動」というより、社会全体のひずみが写した姿なのかもしれないですね…。
news.yahoo.co.jp/articles/15b...
いじめや家庭不和といった明確な原因が見えず、「なんとなく行きたくない」と感じる子が増えているとのこと。文科省の調査でも主因の半数以上が「無気力・不安」とされ本人も理由を言語化できないケースが多いようです。
こうした子どもを「怠け」や「甘え」と誤解し無理に登校を促すと、心身に強いストレスを与えることもあります。
不登校は「原因を探す問題」ではなく「安心を取り戻す支援」が必要な状態と考えます。見えない不安を受け止め、まずは安心して休める環境づくりが第一歩だと感じますね
news.yahoo.co.jp/articles/6eb...

いじめや家庭不和といった明確な原因が見えず、「なんとなく行きたくない」と感じる子が増えているとのこと。文科省の調査でも主因の半数以上が「無気力・不安」とされ本人も理由を言語化できないケースが多いようです。
こうした子どもを「怠け」や「甘え」と誤解し無理に登校を促すと、心身に強いストレスを与えることもあります。
不登校は「原因を探す問題」ではなく「安心を取り戻す支援」が必要な状態と考えます。見えない不安を受け止め、まずは安心して休める環境づくりが第一歩だと感じますね
news.yahoo.co.jp/articles/6eb...
こうした制度がもっと周知されて、少しでも不登校の子どもたちや親の負担が軽くなるといいですね。制度を知って活用することが、進学や将来への不利を減らす一歩になりそうです。
こちら記事になっていました
news.yahoo.co.jp/articles/bdc...

こうした制度がもっと周知されて、少しでも不登校の子どもたちや親の負担が軽くなるといいですね。制度を知って活用することが、進学や将来への不利を減らす一歩になりそうです。
こちら記事になっていました
news.yahoo.co.jp/articles/bdc...
教員手作りの教材や複数教員体制など、個々の背景に寄り添う工夫が随所にみられるのも興味深いです。
学び直しは年齢ではなく「勇気」から始まる。教育の原点を思い出させる、温かい夜の学び舎だと思いました。
教員手作りの教材や複数教員体制など、個々の背景に寄り添う工夫が随所にみられるのも興味深いです。
学び直しは年齢ではなく「勇気」から始まる。教育の原点を思い出させる、温かい夜の学び舎だと思いました。
不登校が過去最多となる中、海外の取組を参考に、日本の支援の在り方を探る狙いです。
不登校はもはや一部の家庭の問題ではなく、社会全体の課題。日本の文化・学校構造に合った「子どもの尊厳を守る支援モデル」を構築していってほしいと感じます。
ちなみにオンライン参加も可能だそうです。
reseed.resemom.jp/article/2025...

不登校が過去最多となる中、海外の取組を参考に、日本の支援の在り方を探る狙いです。
不登校はもはや一部の家庭の問題ではなく、社会全体の課題。日本の文化・学校構造に合った「子どもの尊厳を守る支援モデル」を構築していってほしいと感じます。
ちなみにオンライン参加も可能だそうです。
reseed.resemom.jp/article/2025...
学校復帰を急ぐより、「安心して過ごせる場所」を社会全体で支える視点が必要です。
民間フリースクールとの連携や親の就労支援など、多様な支援策を柔軟に組み合わせ、「孤立させない社会づくり」こそが今、求められていると感じます。
www.yomiuri.co.jp/editorial/20...

学校復帰を急ぐより、「安心して過ごせる場所」を社会全体で支える視点が必要です。
民間フリースクールとの連携や親の就労支援など、多様な支援策を柔軟に組み合わせ、「孤立させない社会づくり」こそが今、求められていると感じます。
www.yomiuri.co.jp/editorial/20...
これまで不登校児の努力や成長が成績に反映されにくかった課題を是正する狙いがあります。
一方で、対象が公的機関に限られ民間フリースクールが除外される方向なのは懸念点。実際には民間で支援を受ける子どもも多く、制度の枠外に置かれることで格差が生まれかねません。
評価制度は「学校に戻すため」ではなく、お子さん一人ひとりの回復と学びを可視化するものであってほしいと思います。
news.yahoo.co.jp/articles/750...

これまで不登校児の努力や成長が成績に反映されにくかった課題を是正する狙いがあります。
一方で、対象が公的機関に限られ民間フリースクールが除外される方向なのは懸念点。実際には民間で支援を受ける子どもも多く、制度の枠外に置かれることで格差が生まれかねません。
評価制度は「学校に戻すため」ではなく、お子さん一人ひとりの回復と学びを可視化するものであってほしいと思います。
news.yahoo.co.jp/articles/750...
不登校の背景には、“わかりやすい理由”だけでなく、本人にも説明できない“心のエネルギーの枯渇”があるという指摘も。
これは「サボり」ではなくまさに「充電が切れた状態」。一度エネルギーが尽きると、寝ても休んでも回復しにくい子が増えているとのがリアルだと思います。
不登校は“問題”ではなく“エネルギーの再充電期間”。
そう捉え直すことで、大人が子どもへの関わり方が変わっていくように思います。
news.yahoo.co.jp/articles/380...

不登校の背景には、“わかりやすい理由”だけでなく、本人にも説明できない“心のエネルギーの枯渇”があるという指摘も。
これは「サボり」ではなくまさに「充電が切れた状態」。一度エネルギーが尽きると、寝ても休んでも回復しにくい子が増えているとのがリアルだと思います。
不登校は“問題”ではなく“エネルギーの再充電期間”。
そう捉え直すことで、大人が子どもへの関わり方が変わっていくように思います。
news.yahoo.co.jp/articles/380...
不登校児童が増える中、受け皿となるフリースクールは人材・予算ともに不足。逃げ場があっても支援が行き届かない状況です。
親は我が子の限界を見極めつつも孤立しがちで、家庭だけで抱えるにはあまりに重い状況に見えます。社会全体で「逃げる」を支える仕組みを整えることが急務だと感じます。
こちらの記事への所感です
news.yahoo.co.jp/articles/702...

不登校児童が増える中、受け皿となるフリースクールは人材・予算ともに不足。逃げ場があっても支援が行き届かない状況です。
親は我が子の限界を見極めつつも孤立しがちで、家庭だけで抱えるにはあまりに重い状況に見えます。社会全体で「逃げる」を支える仕組みを整えることが急務だと感じます。
こちらの記事への所感です
news.yahoo.co.jp/articles/702...
一方で、いじめの認知件数は76万9000件超、暴力行為も過去最多に。SNSなど“見えないいじめ”の増加が背景にあり、重篤化するまで気づかれないケースも目立ちます。
数字の陰にあるのは、子どもたちの「限界のサイン」です。不登校を“問題”ではなく“自己防衛の反応”と捉え直し、家庭・学校・社会が安心して助けを求められる関係性を築けるかが、今まさに問われていますね…。
一方で、いじめの認知件数は76万9000件超、暴力行為も過去最多に。SNSなど“見えないいじめ”の増加が背景にあり、重篤化するまで気づかれないケースも目立ちます。
数字の陰にあるのは、子どもたちの「限界のサイン」です。不登校を“問題”ではなく“自己防衛の反応”と捉え直し、家庭・学校・社会が安心して助けを求められる関係性を築けるかが、今まさに問われていますね…。
その一方、「協働学習」実践校では「中退ゼロ・不登校ゼロ」という成果を挙げており、単なる“遊び”ではなく「学びの本質」に迫る体験が、子どもを変えうるのかもしれません。
不登校の増加が止まらない今、重要なのは「学校に行く/行かない」の二択ではなく、“どういう環境で学び、どう安心できるか”という視点だと感じますね…!
373news.com/news/local/d...

その一方、「協働学習」実践校では「中退ゼロ・不登校ゼロ」という成果を挙げており、単なる“遊び”ではなく「学びの本質」に迫る体験が、子どもを変えうるのかもしれません。
不登校の増加が止まらない今、重要なのは「学校に行く/行かない」の二択ではなく、“どういう環境で学び、どう安心できるか”という視点だと感じますね…!
373news.com/news/local/d...
友人関係のつまずきから学校に行けなくなったお子さんが、母の勧めで出会ったスケートボード。最初は無表情だった少年が、今では笑顔でダンスまで披露できるようになったのは、「好きなこと」を通して自信を取り戻せたからでしょう。
支えたのは、スケボー×福祉を掲げるコーチ。不登校の子も「そのままで受け入れられる」場があったことが大きかったと思います。
不登校支援は、「自分を認めてくれる大人」に出会うこと。「好き」が自信に変わる瞬間を支える社会でありたいですね。
news.yahoo.co.jp/articles/4ae...

友人関係のつまずきから学校に行けなくなったお子さんが、母の勧めで出会ったスケートボード。最初は無表情だった少年が、今では笑顔でダンスまで披露できるようになったのは、「好きなこと」を通して自信を取り戻せたからでしょう。
支えたのは、スケボー×福祉を掲げるコーチ。不登校の子も「そのままで受け入れられる」場があったことが大きかったと思います。
不登校支援は、「自分を認めてくれる大人」に出会うこと。「好き」が自信に変わる瞬間を支える社会でありたいですね。
news.yahoo.co.jp/articles/4ae...
子どもにとって不登校は怠けや反抗ではなく、心や身体がSOSを出している状態。そんな時こそ、「一人じゃない」と感じられる環境が何よりの支えになります。
先生や周囲の大人が、無理に登校を促すのではなく、「最近どう?」とさりげなく声をかけ、どんな小さな言葉にも耳を傾けること。その積み重ねが、お子さんが再び人を信じ、自分を取り戻していく第一歩になるのだと思います。
こちらの記事への所感です
news.yahoo.co.jp/articles/292...

子どもにとって不登校は怠けや反抗ではなく、心や身体がSOSを出している状態。そんな時こそ、「一人じゃない」と感じられる環境が何よりの支えになります。
先生や周囲の大人が、無理に登校を促すのではなく、「最近どう?」とさりげなく声をかけ、どんな小さな言葉にも耳を傾けること。その積み重ねが、お子さんが再び人を信じ、自分を取り戻していく第一歩になるのだと思います。
こちらの記事への所感です
news.yahoo.co.jp/articles/292...
数字の背後には、努力しても報われにくい社会、未来への不安、孤立があります。若者の心が折れる前に、話を聴ける大人・居場所を増やすこともありますが、「命をつなぐ」ことは特別な支援だけでなく、日常の小さな対話からも始まります。
社会全体で若者の“生きづらさ”を受け止める必要があると感じました。
こちらの自殺対策白書に関する記事への所感です。
news.yahoo.co.jp/articles/dee...

数字の背後には、努力しても報われにくい社会、未来への不安、孤立があります。若者の心が折れる前に、話を聴ける大人・居場所を増やすこともありますが、「命をつなぐ」ことは特別な支援だけでなく、日常の小さな対話からも始まります。
社会全体で若者の“生きづらさ”を受け止める必要があると感じました。
こちらの自殺対策白書に関する記事への所感です。
news.yahoo.co.jp/articles/dee...
自然に囲まれた環境で、子どもたちは“生きる実感”を取り戻し、自分のペースで成長していく。親もまた「頑張らせる」から「見守る」へと気持ちを切り替えるきっかけを得られます。
不登校は怠けではなく、環境が合わなかっただけ。100人に100通りの学びがあっていいという0Live学園の姿勢は、教育の多様化を象徴していまづ。学びの原点は「生きる喜び」にある…そう気づかせてくれる事例ですね。
こちらの記事への所感です
news.yahoo.co.jp/articles/c64...

自然に囲まれた環境で、子どもたちは“生きる実感”を取り戻し、自分のペースで成長していく。親もまた「頑張らせる」から「見守る」へと気持ちを切り替えるきっかけを得られます。
不登校は怠けではなく、環境が合わなかっただけ。100人に100通りの学びがあっていいという0Live学園の姿勢は、教育の多様化を象徴していまづ。学びの原点は「生きる喜び」にある…そう気づかせてくれる事例ですね。
こちらの記事への所感です
news.yahoo.co.jp/articles/c64...
藤沢での「朝cafe」や「夜Cafe」など、親子が安心してつながれる居場所づくりを続けています。「学校に行く・行かない」という枠ではなく、「どう生きたいか」を親子で考えるきっかけをくれる活動。
お子さんを変えようとするのではなく、親が社会の見方を変えることから始まる――。
そんな小沼さんの姿勢に、私も共感し、勇気をもらいました。
藤沢での「朝cafe」や「夜Cafe」など、親子が安心してつながれる居場所づくりを続けています。「学校に行く・行かない」という枠ではなく、「どう生きたいか」を親子で考えるきっかけをくれる活動。
お子さんを変えようとするのではなく、親が社会の見方を変えることから始まる――。
そんな小沼さんの姿勢に、私も共感し、勇気をもらいました。
不登校になると、どうしても「お子さんにどう関わるか」ばかりに意識がいきがちですが、実は夫婦の関係も大きなテーマです。
意見が違うと、「どっちが正しいか」でぶつかってしまうけど、本当は「どちらもお子さんを想っている」という点では同じ。
完璧に一致しなくても、「根っこでは同じ方向を見てる」と思えるだけで、少し心が軽くなるのだと感じます。
こちらの記事です
news.yahoo.co.jp/articles/4d9...

不登校になると、どうしても「お子さんにどう関わるか」ばかりに意識がいきがちですが、実は夫婦の関係も大きなテーマです。
意見が違うと、「どっちが正しいか」でぶつかってしまうけど、本当は「どちらもお子さんを想っている」という点では同じ。
完璧に一致しなくても、「根っこでは同じ方向を見てる」と思えるだけで、少し心が軽くなるのだと感じます。
こちらの記事です
news.yahoo.co.jp/articles/4d9...
ですが文科省調査では小中学生の約7~8割が訴え、教師の認識は2割程度と大きなギャップがあり、理解が必要だと感じます。
子どもの「体の声」を見過ごさず、心身両面から寄り添う支援が不可欠ですね。
ですが文科省調査では小中学生の約7~8割が訴え、教師の認識は2割程度と大きなギャップがあり、理解が必要だと感じます。
子どもの「体の声」を見過ごさず、心身両面から寄り添う支援が不可欠ですね。
登校できなかった子どもたちが、別室講義や自由な過ごし方を通じて少しずつ「自分で選ぶ力」を回復し、学校で笑顔を見せるようになる事例が報じられています。学校では許されない「不登校」「授業欠席」も、この場所では許容される選択肢です。
こうした学校の仕組みは、子どもの「自我」を尊重し、回復への入口を開くモデルだと思います。
小さな選択を重ねられる場所が、子どもたちの「生きたい気持ち」を育むかもしれないですね。
mi-mollet.com/articles/-/5...

登校できなかった子どもたちが、別室講義や自由な過ごし方を通じて少しずつ「自分で選ぶ力」を回復し、学校で笑顔を見せるようになる事例が報じられています。学校では許されない「不登校」「授業欠席」も、この場所では許容される選択肢です。
こうした学校の仕組みは、子どもの「自我」を尊重し、回復への入口を開くモデルだと思います。
小さな選択を重ねられる場所が、子どもたちの「生きたい気持ち」を育むかもしれないですね。
mi-mollet.com/articles/-/5...