
僕は図書館で借りて少し読んだのですが、たしかに難しかったですね...
僕は図書館で借りて少し読んだのですが、たしかに難しかったですね...
という感じで、かなり好きな本だったので、感想が長くなってしまった。
(4/4)


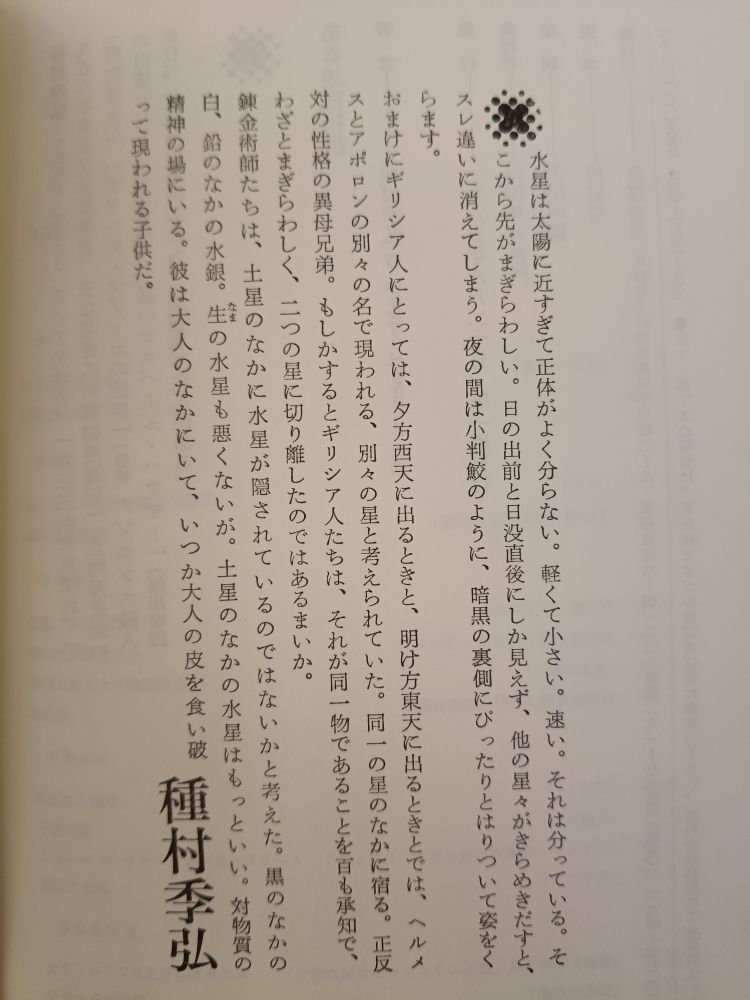
という感じで、かなり好きな本だったので、感想が長くなってしまった。
(4/4)
(3/n)
(3/n)
この断片に関する評は、カフカの断片集や、パスカルの『パンセ』、僕が最近読んだシオランの『崩壊概論』を彷彿とさせる。断片の集積の構造、それが見事に種村季弘によって評されている。
本書の断片、それは万有浮力の法則が支配するクレリチの絵画、ゲーテの球体造形作品、カール・ケレーニイ、神話的職人、ショーペンハウアー……であり、マニエリスムの迷宮が構築されている。
(2/n)
この断片に関する評は、カフカの断片集や、パスカルの『パンセ』、僕が最近読んだシオランの『崩壊概論』を彷彿とさせる。断片の集積の構造、それが見事に種村季弘によって評されている。
本書の断片、それは万有浮力の法則が支配するクレリチの絵画、ゲーテの球体造形作品、カール・ケレーニイ、神話的職人、ショーペンハウアー……であり、マニエリスムの迷宮が構築されている。
(2/n)
・知性の力が言葉の上に光彩を投じ、言葉を磨いてきらきら光らせようとする。この力の組織化されたものが、いわゆる文化である──虚無の大空に打ち上げられる花火なのである。
・崩壊は生命の法則の第一の定めである。われわれは、無生物が塵と化すよりも先に崩壊して塵となり、星々の見守る下で、われわれ自身の運命の定めるところにまっしぐらに駆けて行くのだ。もっとも星々にしたところで、見かけは永劫不滅でも、この宇宙のなかでやがてぼろぼろに崩れていく。
・知性の力が言葉の上に光彩を投じ、言葉を磨いてきらきら光らせようとする。この力の組織化されたものが、いわゆる文化である──虚無の大空に打ち上げられる花火なのである。
・崩壊は生命の法則の第一の定めである。われわれは、無生物が塵と化すよりも先に崩壊して塵となり、星々の見守る下で、われわれ自身の運命の定めるところにまっしぐらに駆けて行くのだ。もっとも星々にしたところで、見かけは永劫不滅でも、この宇宙のなかでやがてぼろぼろに崩れていく。

