
分厚すぎるのが難点だけど、ランダムに短編を読むのにちょうど良い。
なろう系でもAIを扱ったSFはいっぱいある。生成AIという会話ができるタイプがプレークスルーだったのと、「幻想(ハルシネーション)」という形でAIも間違えるってのが納得できる現象として広まったからだろう。
昔の冷たい人工知能とは違う描き方が多い。

分厚すぎるのが難点だけど、ランダムに短編を読むのにちょうど良い。
なろう系でもAIを扱ったSFはいっぱいある。生成AIという会話ができるタイプがプレークスルーだったのと、「幻想(ハルシネーション)」という形でAIも間違えるってのが納得できる現象として広まったからだろう。
昔の冷たい人工知能とは違う描き方が多い。
実写には映画と演劇だろうか?

実写には映画と演劇だろうか?
将棋なんて中学生以来なので、戦法としては棒銀と穴熊しか知りません。
先週の連休前にスマホで将棋ウォーズを入れて、さすがにこれでは勝てないので銀矢倉を覚えて6級をうろうろという状態。で、もう少し頑張れるかなと思って、将棋盤を購入。

将棋なんて中学生以来なので、戦法としては棒銀と穴熊しか知りません。
先週の連休前にスマホで将棋ウォーズを入れて、さすがにこれでは勝てないので銀矢倉を覚えて6級をうろうろという状態。で、もう少し頑張れるかなと思って、将棋盤を購入。


IT の設計も似たようなもので、こうしたらいいんじゃないかという想像力が大事なんだけど、余計なものを足し過ぎて失敗している例もあるから、想像力だけではだめですね。整合性が合うように論理思考力がないと駄目だし。

IT の設計も似たようなもので、こうしたらいいんじゃないかという想像力が大事なんだけど、余計なものを足し過ぎて失敗している例もあるから、想像力だけではだめですね。整合性が合うように論理思考力がないと駄目だし。
【理数探究】高校数学の探究学習事例5つを紹介 - Far East Tokyo www.blog.studyvalley.jp/2021/08/24/m...

【理数探究】高校数学の探究学習事例5つを紹介 - Far East Tokyo www.blog.studyvalley.jp/2021/08/24/m...
適当に探究レポートを突っ込んで、どこどこを書き加えれば、評点があがりますよ、って示してくれるだけで良い。学校の内申対策なので :)

適当に探究レポートを突っ込んで、どこどこを書き加えれば、評点があがりますよ、って示してくれるだけで良い。学校の内申対策なので :)
ゼンゲのほうはチームビルディングからスタートするのだが、アメーバ経営はチームは組んでしまってあって目標値を明確にするところからスタートする。後者のほうは、勤勉な日本人としては達成感が得られる。ある意味で、自分で目標を立てられない日本人向きとも言える。

ゼンゲのほうはチームビルディングからスタートするのだが、アメーバ経営はチームは組んでしまってあって目標値を明確にするところからスタートする。後者のほうは、勤勉な日本人としては達成感が得られる。ある意味で、自分で目標を立てられない日本人向きとも言える。
AI チャットで会話しながら、要件&機能を進めていくと、見積もりのための機能/非機能/概要を IT 屋向けにまとめてくれる仕組み。どうリーチさせるかは検討課題だけど、官庁の入札やクラウドワークスの依頼書に載せられるレベルまでには行く予定。

AI チャットで会話しながら、要件&機能を進めていくと、見積もりのための機能/非機能/概要を IT 屋向けにまとめてくれる仕組み。どうリーチさせるかは検討課題だけど、官庁の入札やクラウドワークスの依頼書に載せられるレベルまでには行く予定。
Claude Sonnet を使いながら React Native Expo で超小遣い帳を作ってみている。スマホの Copilot でぼちぼちと設計しながら、VSCode の設計 .md を使って Claude Sonnet を使う。
大雑把な画面設定(タイトルや項目名ぐらい)だけ Copilot で設定して、細かい UI は Claude Sonnet まかせ。確かに、このパターンだと非IT業者でもできそうだが、設計を作るのが難しいだろう。


Claude Sonnet を使いながら React Native Expo で超小遣い帳を作ってみている。スマホの Copilot でぼちぼちと設計しながら、VSCode の設計 .md を使って Claude Sonnet を使う。
大雑把な画面設定(タイトルや項目名ぐらい)だけ Copilot で設定して、細かい UI は Claude Sonnet まかせ。確かに、このパターンだと非IT業者でもできそうだが、設計を作るのが難しいだろう。

ぐるぐるサイクルだけ示すより、こうやったほうが解りやすいのでは?
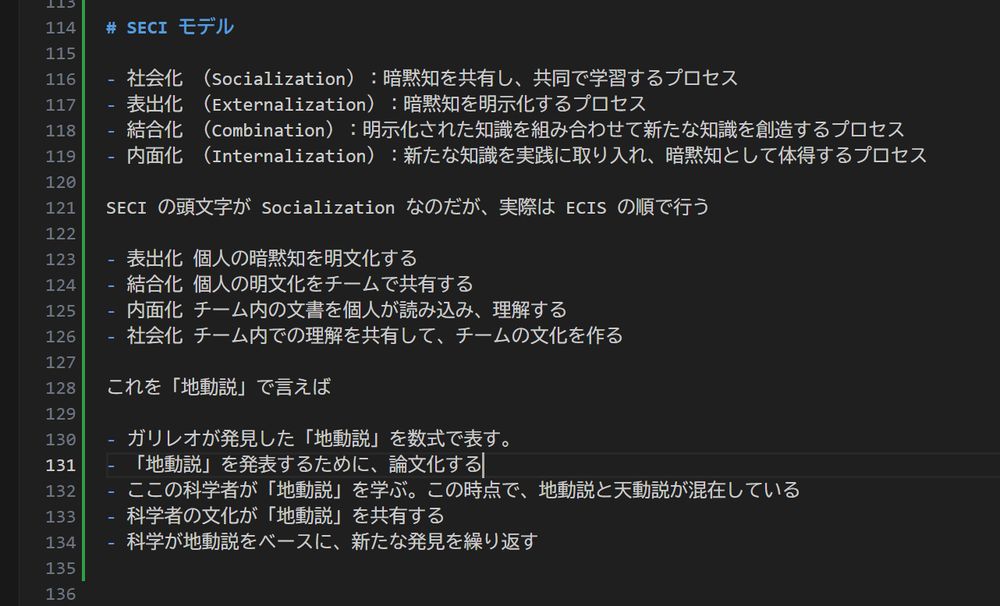
ぐるぐるサイクルだけ示すより、こうやったほうが解りやすいのでは?


これは裁判所なので、妥当な判決。
まあ、現状においても企業献金のリスクはこれが伴う訳で、同じく宗教的な献金も似た感じなわけですが。旧統一教会の選挙ボランティアとか無償秘書なんてのは、実質、外資による企業献金ですからね。

これは裁判所なので、妥当な判決。
まあ、現状においても企業献金のリスクはこれが伴う訳で、同じく宗教的な献金も似た感じなわけですが。旧統一教会の選挙ボランティアとか無償秘書なんてのは、実質、外資による企業献金ですからね。
興味深いのは、裁判所としては企業献金が政党政治の買収に当たる可能性ありと示しつつも、買収は結果に過ぎない副作用である、という解釈をしていること。
実際のところ、法人格は法人税として税金を納めているので、自然人と同じように法人として献金ができるのは確かではある。しかし、参政権はないのだが。
まあ、確かにこの裁判では「取締役の企業献金が、会社にとって(特に従業員にとって)利益相反になる行為であるか?」という裁判なので、それによる買収行為等は副作用に過ぎませんよね、ってところなので、企業献金そのものの可否とは関係ないですね。
にしても、企業献金を問うならば民法の範囲だと思う。


興味深いのは、裁判所としては企業献金が政党政治の買収に当たる可能性ありと示しつつも、買収は結果に過ぎない副作用である、という解釈をしていること。
実際のところ、法人格は法人税として税金を納めているので、自然人と同じように法人として献金ができるのは確かではある。しかし、参政権はないのだが。
まあ、確かにこの裁判では「取締役の企業献金が、会社にとって(特に従業員にとって)利益相反になる行為であるか?」という裁判なので、それによる買収行為等は副作用に過ぎませんよね、ってところなので、企業献金そのものの可否とは関係ないですね。
にしても、企業献金を問うならば民法の範囲だと思う。

が2%止まりなのは、所謂少数派であって統計的には外れ値扱いになる。
なる…が、それぞれ10万人程度の支持があったわけで、少数派としての戦い方(つまりはゲリラ戦)となる。安野氏のポスター貼りの手法は一見IT活用の賢い作戦のように見えるが、それはまさしく賢いゲリラ戦だ。つまりは、最初から少数派であることを自認しているやり方になる。
暇空氏の顔を出さない手法もゲリラ戦の手法で、一定のコアな支持層は集められるがそれ以上には広がらない。
組織長は無理でも区議選に出て議員からスタートすると当選できるかもしれない…が、二人ともそれはやらないだろうなぁ。

が2%止まりなのは、所謂少数派であって統計的には外れ値扱いになる。
なる…が、それぞれ10万人程度の支持があったわけで、少数派としての戦い方(つまりはゲリラ戦)となる。安野氏のポスター貼りの手法は一見IT活用の賢い作戦のように見えるが、それはまさしく賢いゲリラ戦だ。つまりは、最初から少数派であることを自認しているやり方になる。
暇空氏の顔を出さない手法もゲリラ戦の手法で、一定のコアな支持層は集められるがそれ以上には広がらない。
組織長は無理でも区議選に出て議員からスタートすると当選できるかもしれない…が、二人ともそれはやらないだろうなぁ。

ただ、投票率55%程度で投票数600万の場合、200万票から150万票がボーダーラインなので、かなりのところまではいけるはず。
1drv.ms/x/s!AmXmBbui...

ただ、投票率55%程度で投票数600万の場合、200万票から150万票がボーダーラインなので、かなりのところまではいけるはず。
1drv.ms/x/s!AmXmBbui...





