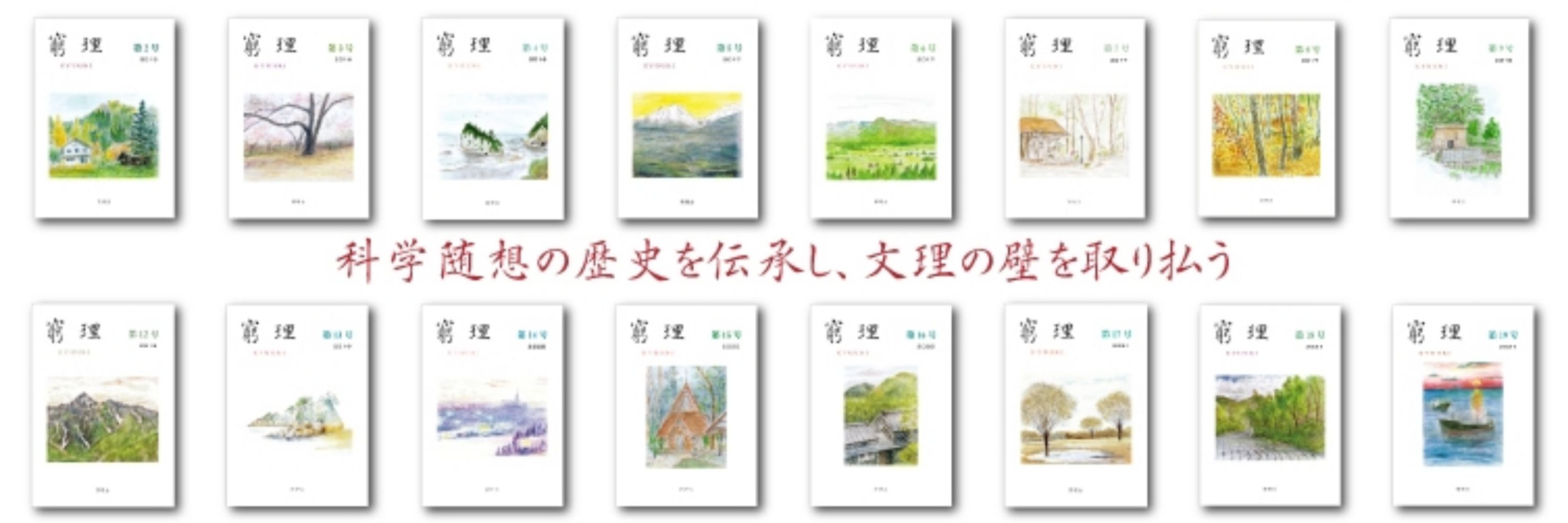
書店でお求めの方は、こちらのページを店員さんにお見せ下さい。
https://kyuurisha.com/info-bookstore/
ハガキの背景に透かしで挿入している蟠桃の文についても、同じく池内先生の随筆に訳が説明されています。蟠桃は現代宇宙論に匹敵する宇宙観を持っており、私たちと似たような知性をもった生物が他の惑星にもいるであろうことを指摘しています。

ハガキの背景に透かしで挿入している蟠桃の文についても、同じく池内先生の随筆に訳が説明されています。蟠桃は現代宇宙論に匹敵する宇宙観を持っており、私たちと似たような知性をもった生物が他の惑星にもいるであろうことを指摘しています。
ハガキの背景に透かしで挿入している梅園の詩は、長崎洋学の最高峰といわれた吉雄耕牛との思い出を綴ったものです。梅園は耕牛から多くを長崎の地で学びました。彼の原点をうかがい知る詩の一篇です。

ハガキの背景に透かしで挿入している梅園の詩は、長崎洋学の最高峰といわれた吉雄耕牛との思い出を綴ったものです。梅園は耕牛から多くを長崎の地で学びました。彼の原点をうかがい知る詩の一篇です。
絵はがきは、小誌で取り上げたことがある江戸時代の窮理学師、三浦梅園と山片蟠桃がモチーフ。
それぞれ医者と商人をイメージしたカラーにしていただきました!
絵はがきは、小誌で取り上げたことがある江戸時代の窮理学師、三浦梅園と山片蟠桃がモチーフ。
それぞれ医者と商人をイメージしたカラーにしていただきました!
古書善行堂さん
zenkohdo.shop-pro.jp
蟲文庫さん
mushi-bunko.com
機械書房さん
machinebooks.base.shop/items/118844...
ジュンク堂池袋本店さん(1F)
honto.jp/store/detail...
丸善名古屋本店さん(4F)
honto.jp/store/detail...
書泉グランデさん(4F)
www.shosen.co.jp
お近くの方はぜひ行ってみてください!


古書善行堂さん
zenkohdo.shop-pro.jp
蟲文庫さん
mushi-bunko.com
機械書房さん
machinebooks.base.shop/items/118844...
ジュンク堂池袋本店さん(1F)
honto.jp/store/detail...
丸善名古屋本店さん(4F)
honto.jp/store/detail...
書泉グランデさん(4F)
www.shosen.co.jp
お近くの方はぜひ行ってみてください!
今年はラジオ放送100周年。初放送は1925年3月22日9:30の発信。耳の敏感な寅彦先生には、放送当初のラジオの音はどんな印象だったでしょう…
今年はラジオ放送100周年。初放送は1925年3月22日9:30の発信。耳の敏感な寅彦先生には、放送当初のラジオの音はどんな印象だったでしょう…
名だたる世界中の物理学者との思い出を綴る本連載は佐藤先生の人としての親交の深さを物語るものでした
黙祷
名だたる世界中の物理学者との思い出を綴る本連載は佐藤先生の人としての親交の深さを物語るものでした
黙祷
こうした話題は、AI研究にも関わるもので、例えば九鬼の『偶然性の問題』での因果系列の話は、AIと因果推論の問題に広げたら面白そうです…
こうした話題は、AI研究にも関わるもので、例えば九鬼の『偶然性の問題』での因果系列の話は、AIと因果推論の問題に広げたら面白そうです…
宋代から伝わる、世界に3碗しかない曜変天目茶碗をめぐる研究で見出された美しさの秘密とは何か…
科学と芸術が交差する世界、そして研究者を魅了する「輝き」を味わってみてください。
宋代から伝わる、世界に3碗しかない曜変天目茶碗をめぐる研究で見出された美しさの秘密とは何か…
科学と芸術が交差する世界、そして研究者を魅了する「輝き」を味わってみてください。
落ち込んだ時ほど人の感情に影響を与えるものって何でしょう…
西さんの自然界への気づきと発見が、叙情味ゆたかに綴られるアイスクリーム文学と言ってもよい秀作。
落ち込んだ時ほど人の感情に影響を与えるものって何でしょう…
西さんの自然界への気づきと発見が、叙情味ゆたかに綴られるアイスクリーム文学と言ってもよい秀作。
入学する年に肋膜炎になってしまい休学も多かった仁科先生に、進学の相談など親身にのってくれた恩師・松尾哲太郎が登場します。
温情に溢れていた松尾先生は、後の仁科芳雄のロールモデルかもしれません。
入学する年に肋膜炎になってしまい休学も多かった仁科先生に、進学の相談など親身にのってくれた恩師・松尾哲太郎が登場します。
温情に溢れていた松尾先生は、後の仁科芳雄のロールモデルかもしれません。
今回は、戦争で疲弊した祖国をショパンが想って作った歌曲「舞い落ちる木の葉」(作詞ポル)を取りあげ、AIが模倣できない表現の深層に迫ります。
芸術の本質を問う根源的なテーマであり、検閲と未発表作品と創造の関係についても考えさせられる内容です。
今回は、戦争で疲弊した祖国をショパンが想って作った歌曲「舞い落ちる木の葉」(作詞ポル)を取りあげ、AIが模倣できない表現の深層に迫ります。
芸術の本質を問う根源的なテーマであり、検閲と未発表作品と創造の関係についても考えさせられる内容です。
当時は現代のような査読つき論文発表の場ではなく、情報の報知・交換が主であったことがフォーカスされます。
前回、秦皖梅氏に紹介いただいた『ネイチャー』投稿欄との関連など、その伝統の受容も注目です。
当時は現代のような査読つき論文発表の場ではなく、情報の報知・交換が主であったことがフォーカスされます。
前回、秦皖梅氏に紹介いただいた『ネイチャー』投稿欄との関連など、その伝統の受容も注目です。
難解な量子力学の概念を、台詞や演出をいかに工夫して観客に体感させるか、さらに俳優の役割や表現を通して、科学と演劇の境界に挑む舞台を疑似体験してみてください。
難解な量子力学の概念を、台詞や演出をいかに工夫して観客に体感させるか、さらに俳優の役割や表現を通して、科学と演劇の境界に挑む舞台を疑似体験してみてください。
誤解が随筆の種となる…
ならば、誤解は理解のための大事な摩擦と言えるのではないか?
SNSなら炎上するようなネタも書き手によっては上質な随筆になる、その違いこそ「文」のなせる「芸」なのでしょう。
誤解が随筆の種となる…
ならば、誤解は理解のための大事な摩擦と言えるのではないか?
SNSなら炎上するようなネタも書き手によっては上質な随筆になる、その違いこそ「文」のなせる「芸」なのでしょう。

