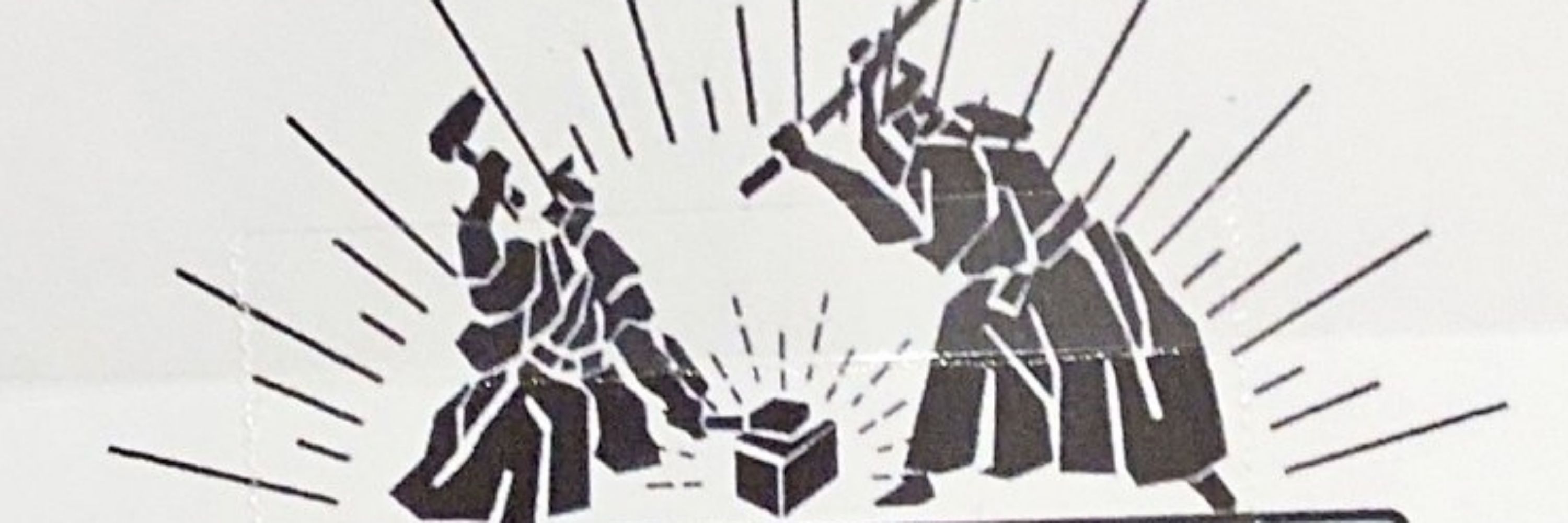
孫六兼元はご近所の憧れのおにいさん
美濃伝&末っ子兼さんかわいがり気味
旅行が好きなのであちこち出没します
会いに来たよ人間無骨!!とテンションMAXで写真撮影していたら、係の方が「喜んでいただける方が多くて嬉しいです。お借りした甲斐がありました☺️」と喜んでらした。
天保に作られた写しで戦場での使用された事はないだろうからこれが元々の薄さだったのかな🤔
係の方も「本物をよく写していると思う」と言ってらしたし、本物もこの薄さだったら斬れ味良さそうですよねーとめっちゃ盛り上がりました。




会いに来たよ人間無骨!!とテンションMAXで写真撮影していたら、係の方が「喜んでいただける方が多くて嬉しいです。お借りした甲斐がありました☺️」と喜んでらした。
天保に作られた写しで戦場での使用された事はないだろうからこれが元々の薄さだったのかな🤔
係の方も「本物をよく写していると思う」と言ってらしたし、本物もこの薄さだったら斬れ味良さそうですよねーとめっちゃ盛り上がりました。



関商工会議所創立70周年記念行事として関鍛冶伝承館の隣の春日神社で開催された薪能を観覧して参りました。
ここで能が舞われるのは150年振りなんだそうで😳
16世紀中頃には正月28日に神事能が行われており、関の刀匠自ら能を奉納していました。
この神事は『刀職者以外には見ることができない』と厳しく定められたものだったのですが、江戸時代には神事能の日以外にも町衆が能を催すようになっていったのだとか。
しかし、その際も『鍛冶方の席を設け、鍛冶方を招待すること』『能舞台と御拝殿の間には座席は設けないこと(神様に舞台がよく見えるように)』などのルールが決められていたようです。


関商工会議所創立70周年記念行事として関鍛冶伝承館の隣の春日神社で開催された薪能を観覧して参りました。
ここで能が舞われるのは150年振りなんだそうで😳
16世紀中頃には正月28日に神事能が行われており、関の刀匠自ら能を奉納していました。
この神事は『刀職者以外には見ることができない』と厳しく定められたものだったのですが、江戸時代には神事能の日以外にも町衆が能を催すようになっていったのだとか。
しかし、その際も『鍛冶方の席を設け、鍛冶方を招待すること』『能舞台と御拝殿の間には座席は設けないこと(神様に舞台がよく見えるように)』などのルールが決められていたようです。
「命売ります」 1/2
同名の小説パロを書きたかった




「命売ります」 1/2
同名の小説パロを書きたかった




様々な文献や関に伝わる伝承では兼定と兼元は師弟関係にあったと伝わっていますが、関係性は2つの説があります。
① 初代兼定(親兼定) の弟子は、二代兼定(㝎定)と二代兼元(孫六兼元)
②初代兼定(親兼定) の弟子は、二代兼定(㝎定)と初代兼元(清関兼元)
主流なのは①だと思いますが、作刀時期から考察すると②の方が有り得そうです。

様々な文献や関に伝わる伝承では兼定と兼元は師弟関係にあったと伝わっていますが、関係性は2つの説があります。
① 初代兼定(親兼定) の弟子は、二代兼定(㝎定)と二代兼元(孫六兼元)
②初代兼定(親兼定) の弟子は、二代兼定(㝎定)と初代兼元(清関兼元)
主流なのは①だと思いますが、作刀時期から考察すると②の方が有り得そうです。
一説には、刀匠・孫六兼元の法名は『大吉』であり『大吉兼元』と銘をきったものもあるという──
「孫六は千代を賀したる婿引出、めでたづくしの大吉兼元とは俺のこと!」

一説には、刀匠・孫六兼元の法名は『大吉』であり『大吉兼元』と銘をきったものもあるという──
「孫六は千代を賀したる婿引出、めでたづくしの大吉兼元とは俺のこと!」
参考資料を元に刀’の銘や情報・刀’工’の関係を調べて私なりにまとめました
※間違っている可能性が大いにあります!
※歌’仙’、無’骨’の作’刀’時期については大体の予想

参考資料を元に刀’の銘や情報・刀’工’の関係を調べて私なりにまとめました
※間違っている可能性が大いにあります!
※歌’仙’、無’骨’の作’刀’時期については大体の予想












