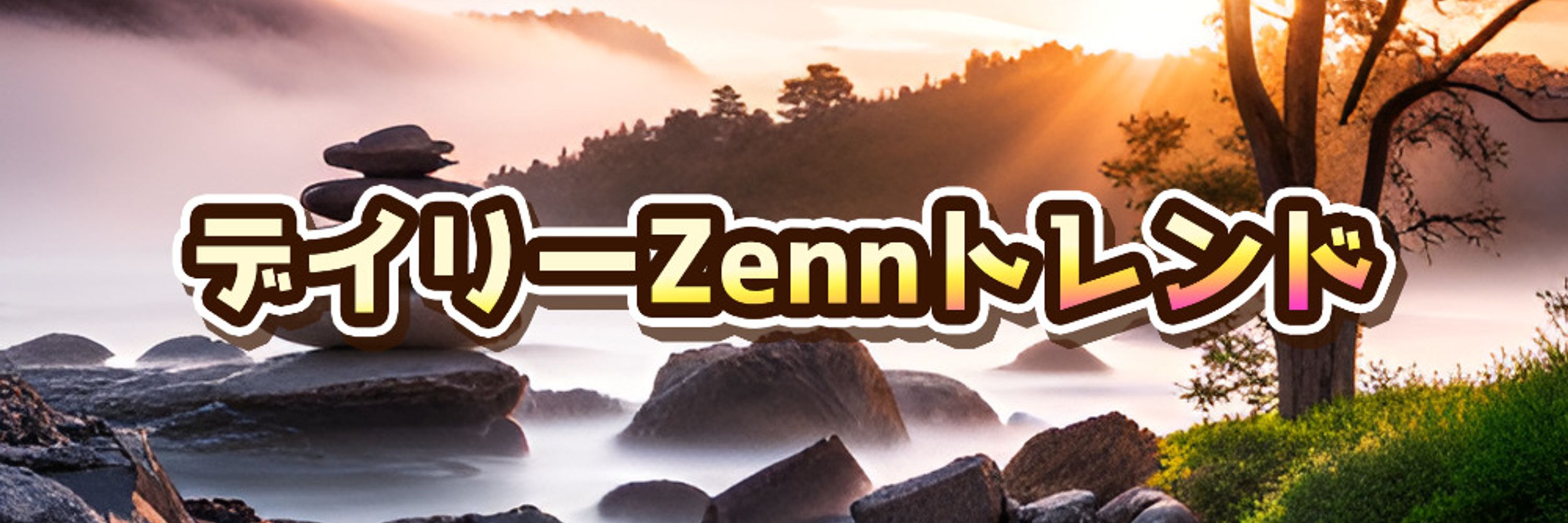
ソースコードの配布は「 https://github.com/aegisfleet/zenn-trending-to-bluesky 」で行っています。
Qiitaトレンド: @dailyqiitatrends.bsky.social
GitHubトレンド: @dailygithubtrends.bsky.social
デカルトの4つの規則に学ぶエンジニアの思考法
本記事は、近代哲学の父デカルトが不確実な時代に確立した「4つの規則」(明証性、分析、総合性、枚挙)が、現代のエンジニアリングにおける強力な思考フレームワークとなり得ることを論じています。
この知的プロセスは、AI時代における情報の信頼性確認、障害発生時の問題切り分け、複雑な機能の実装手順、テストの網羅性チェックなど、多岐にわたる知的労働の場面で応用可能であり、不確実な世界を生き抜くための指針となると提言しています。
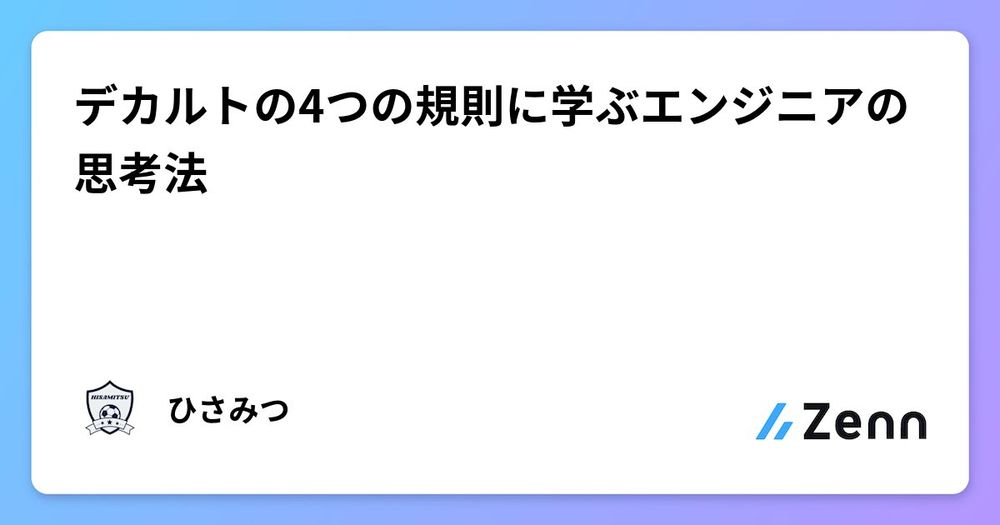
デカルトの4つの規則に学ぶエンジニアの思考法
本記事は、近代哲学の父デカルトが不確実な時代に確立した「4つの規則」(明証性、分析、総合性、枚挙)が、現代のエンジニアリングにおける強力な思考フレームワークとなり得ることを論じています。
この知的プロセスは、AI時代における情報の信頼性確認、障害発生時の問題切り分け、複雑な機能の実装手順、テストの網羅性チェックなど、多岐にわたる知的労働の場面で応用可能であり、不確実な世界を生き抜くための指針となると提言しています。
【Playwright Test Agent】LLMを使ってE2Eテストの開発・保守コストを10分の1にできた、かも
Playwright Test AgentsとClaude Codeを組み合わせ、E2Eテストのテストケース作成、コード生成、修正といった開発・保守作業の大部分をLLMに丸投げすることに成功した事例を紹介。
これにより、テストコードの調整やガイドライン整備にかかる工数を大幅に削減でき、専門知識なしでE2Eテストを運用できる体制を構築できた。

【Playwright Test Agent】LLMを使ってE2Eテストの開発・保守コストを10分の1にできた、かも
Playwright Test AgentsとClaude Codeを組み合わせ、E2Eテストのテストケース作成、コード生成、修正といった開発・保守作業の大部分をLLMに丸投げすることに成功した事例を紹介。
これにより、テストコードの調整やガイドライン整備にかかる工数を大幅に削減でき、専門知識なしでE2Eテストを運用できる体制を構築できた。
FlutterKaigi 2025 参加レポート
FlutterKaigi 2025の参加レポートとして、主要セッションのメモと感想をまとめている。
Flutter DevToolsを用いたパフォーマンス改善、KPIやSLOに基づくUI/UX設計、AI活用、環境整備など、多岐にわたる最新の知見を得た。
特にパフォーマンス改善や監視体制の構築に関する学びは、自身のプロジェクトにすぐに活かしたい内容が多かったと述べている。

FlutterKaigi 2025 参加レポート
FlutterKaigi 2025の参加レポートとして、主要セッションのメモと感想をまとめている。
Flutter DevToolsを用いたパフォーマンス改善、KPIやSLOに基づくUI/UX設計、AI活用、環境整備など、多岐にわたる最新の知見を得た。
特にパフォーマンス改善や監視体制の構築に関する学びは、自身のプロジェクトにすぐに活かしたい内容が多かったと述べている。
隠線処理の話
分子動力学シミュレーション結果の可視化に必要な、3次元直方体の隠線処理(ワイヤーフレームの見えない部分を消す処理)の実装手法を解説する。
本稿では、凸多面体に適用可能で単純な法線ベクトル法を採用した。
この原理は、回転後の各面の法線ベクトルと視線ベクトルの内積を計算し、面が手前向きか奥向きかを判定することに基づく。
辺の可視性は、その辺に接する二つの面のうち、少なくとも一方が手前側を向いている場合に「見える」と判定する論理により決定される。
具体的な頂点・面・辺のインデックス定義と、Python/NumPyを用いた実装ロジックを示した。
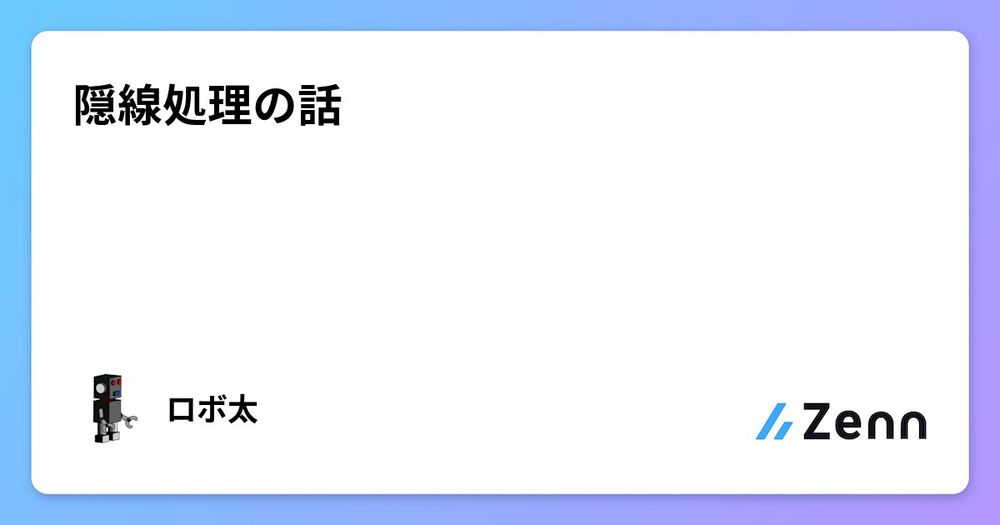
隠線処理の話
分子動力学シミュレーション結果の可視化に必要な、3次元直方体の隠線処理(ワイヤーフレームの見えない部分を消す処理)の実装手法を解説する。
本稿では、凸多面体に適用可能で単純な法線ベクトル法を採用した。
この原理は、回転後の各面の法線ベクトルと視線ベクトルの内積を計算し、面が手前向きか奥向きかを判定することに基づく。
辺の可視性は、その辺に接する二つの面のうち、少なくとも一方が手前側を向いている場合に「見える」と判定する論理により決定される。
具体的な頂点・面・辺のインデックス定義と、Python/NumPyを用いた実装ロジックを示した。
その分析、Cursorにやらせてみませんか?
定例のデータサマリ作成とSlack投稿の自動化を目指し、Cursor(AI分析)とSnowflake、Slackを連携させたレポートシステムを構築しました。
この仕組みは、Snowflakeから取得したデータを元に、AIがYAML定義に基づきMarkdownレポートを自動生成し、GitHub Actionsで定期的にSlackへ投稿します。
これにより、分析者はSQLとレポート定義を書くだけで済み、データ分析業務の効率化と運用柔軟性を高めます。

その分析、Cursorにやらせてみませんか?
定例のデータサマリ作成とSlack投稿の自動化を目指し、Cursor(AI分析)とSnowflake、Slackを連携させたレポートシステムを構築しました。
この仕組みは、Snowflakeから取得したデータを元に、AIがYAML定義に基づきMarkdownレポートを自動生成し、GitHub Actionsで定期的にSlackへ投稿します。
これにより、分析者はSQLとレポート定義を書くだけで済み、データ分析業務の効率化と運用柔軟性を高めます。
【速報記事】FlutterKaigi2025 現地参加レポート
FlutterKaigi 2025の参加レポートとして、iOS対応の迅速さ、DevToolsによるパフォーマンス改善、ビルドキャッシュの仕組み、AI駆動E2Eテストの現状、RenderObjectを用いたアニメーション、AST活用、アプリセキュリティ対策など、Flutter開発における多岐にわたる技術的な学びと知見を共有する。

【速報記事】FlutterKaigi2025 現地参加レポート
FlutterKaigi 2025の参加レポートとして、iOS対応の迅速さ、DevToolsによるパフォーマンス改善、ビルドキャッシュの仕組み、AI駆動E2Eテストの現状、RenderObjectを用いたアニメーション、AST活用、アプリセキュリティ対策など、Flutter開発における多岐にわたる技術的な学びと知見を共有する。
MoonBit 最高 2025
MoonBitは、TypeScriptの不安定さやRustの低レベルさの不満を解決する静的型付け関数型言語である。
Rust風の構文やパターンマッチ、生成コードの小ささなど多くの優れた特徴を持ち、筆者はReactバインディングを作成して実用性を確認した。
しかし、言語仕様は頻繁に変更されており、特に非同期処理やネイティブバックエンドの実装が不安定という課題がある。
機能は充実しつつあるものの、安定性を考慮すると2026年の1.0リリースを待つことも推奨される。
(170文字)

MoonBit 最高 2025
MoonBitは、TypeScriptの不安定さやRustの低レベルさの不満を解決する静的型付け関数型言語である。
Rust風の構文やパターンマッチ、生成コードの小ささなど多くの優れた特徴を持ち、筆者はReactバインディングを作成して実用性を確認した。
しかし、言語仕様は頻繁に変更されており、特に非同期処理やネイティブバックエンドの実装が不安定という課題がある。
機能は充実しつつあるものの、安定性を考慮すると2026年の1.0リリースを待つことも推奨される。
(170文字)
laravelコマンドで Starter Kit を展開し、Sail で固める Laravel 開発環境構築ガイド
DockerとLaravel Sailを活用し、ローカル環境にPHPやComposerをインストールせずにLaravelプロジェクトを迅速に展開する手順を解説する。
この方法により、依存関係の問題を回避し、テスト環境を自動構築できる。
さらに、Sailで導入された最新のPHPバージョンがデプロイ先と異なる場合に、本番環境に合わせるためのバージョン調整方法まで詳述する、実践的な開発環境構築ガイドである。

laravelコマンドで Starter Kit を展開し、Sail で固める Laravel 開発環境構築ガイド
DockerとLaravel Sailを活用し、ローカル環境にPHPやComposerをインストールせずにLaravelプロジェクトを迅速に展開する手順を解説する。
この方法により、依存関係の問題を回避し、テスト環境を自動構築できる。
さらに、Sailで導入された最新のPHPバージョンがデプロイ先と異なる場合に、本番環境に合わせるためのバージョン調整方法まで詳述する、実践的な開発環境構築ガイドである。
nvim-submode : 直感的に設定可能な新しいサブモードプラグイン
Neovim向けの新プラグイン「nvim-submode」が公開されました。
これはLuaで書かれ、独自のモードを作成し、複雑なキーバインドや冗長な繰り返し操作を簡略化する強力な機能を提供します。
大きな特長は、任意のキーにマッチする特殊キー`
これにより、CAPSLOCKモードがわずか8行で実現できるなど、従来困難だった機能も宣言的かつ直感的に定義可能となり、簡潔で強力なカスタマイズ環境を提供します。

nvim-submode : 直感的に設定可能な新しいサブモードプラグイン
Neovim向けの新プラグイン「nvim-submode」が公開されました。
これはLuaで書かれ、独自のモードを作成し、複雑なキーバインドや冗長な繰り返し操作を簡略化する強力な機能を提供します。
大きな特長は、任意のキーにマッチする特殊キー`
これにより、CAPSLOCKモードがわずか8行で実現できるなど、従来困難だった機能も宣言的かつ直感的に定義可能となり、簡潔で強力なカスタマイズ環境を提供します。
チームのCLAUDE.mdが勝手に育つ - Hook機能での自動化
AI開発環境において、チームのルール集(CLAUDE.md)の更新漏れを防ぐため、Claude CodeのHook機能で自動化を実現した。
会話セッション終了時などに履歴を分析し、ルール追加の提案を自動的に行うことで、継続的なガイドラインの改善と運用定着を図る。

チームのCLAUDE.mdが勝手に育つ - Hook機能での自動化
AI開発環境において、チームのルール集(CLAUDE.md)の更新漏れを防ぐため、Claude CodeのHook機能で自動化を実現した。
会話セッション終了時などに履歴を分析し、ルール追加の提案を自動的に行うことで、継続的なガイドラインの改善と運用定着を図る。
Moonbit で React アプリを書く
著者はMoonbitを日常的に活用するため、JSバックエンドとFFIを使ってReactアプリケーション開発を試みた。
Reactプログラマに自然なAPIを提供すべく、DOMやReactなどへのJSバインディングを独自に実装し、カウンターコンポーネントの作成とテストに成功した。
この取り組みは、TypeScriptの不安定性やマンネリからの脱却を図り、Moonbitが現実のユースケースに対応できるポテンシャルを持つことを示す挑戦である。

Moonbit で React アプリを書く
著者はMoonbitを日常的に活用するため、JSバックエンドとFFIを使ってReactアプリケーション開発を試みた。
Reactプログラマに自然なAPIを提供すべく、DOMやReactなどへのJSバインディングを独自に実装し、カウンターコンポーネントの作成とテストに成功した。
この取り組みは、TypeScriptの不安定性やマンネリからの脱却を図り、Moonbitが現実のユースケースに対応できるポテンシャルを持つことを示す挑戦である。
書いたコードを“スキル化”して再利用してる話
本記事は、Claude CodeのAgent Skills機能を利用し、定型的なコードを効率的に再利用する方法を紹介しています。
データストアアクセスにおけるRepositoryパターンなど、繰り返し発生するパターンコードの手動作成の手間や、従来のLLM利用時の品質課題を解決するため、公式の「skill creator」スキルを活用します。
既存のコード(git diffなど)を入力することで、自動的にプロジェクト標準に合致した高品質なテンプレート(スキル)を作成し、これを再利用することで開発の生産性向上を実現します。

書いたコードを“スキル化”して再利用してる話
本記事は、Claude CodeのAgent Skills機能を利用し、定型的なコードを効率的に再利用する方法を紹介しています。
データストアアクセスにおけるRepositoryパターンなど、繰り返し発生するパターンコードの手動作成の手間や、従来のLLM利用時の品質課題を解決するため、公式の「skill creator」スキルを活用します。
既存のコード(git diffなど)を入力することで、自動的にプロジェクト標準に合致した高品質なテンプレート(スキル)を作成し、これを再利用することで開発の生産性向上を実現します。
Python で他生物の視覚をシミュレートする
本記事は、生物の擬態を人間目線ではなく、実際の捕食者(ベラの一種)の視覚特性から評価するシミュレーション手法を紹介します。
PythonとGoogle Colabを用い、文献データに基づきベラの三種の錐体感度カーブを再現。
さらに、水中での光の減衰やぼかしなどの環境効果を加味し、RGB画像を捕食者の錐体刺激空間へ変換する詳細な技術的プロセスを解説しています。
これにより、対象生物が捕食者にどう見えているかを探ることを目的としています。

Python で他生物の視覚をシミュレートする
本記事は、生物の擬態を人間目線ではなく、実際の捕食者(ベラの一種)の視覚特性から評価するシミュレーション手法を紹介します。
PythonとGoogle Colabを用い、文献データに基づきベラの三種の錐体感度カーブを再現。
さらに、水中での光の減衰やぼかしなどの環境効果を加味し、RGB画像を捕食者の錐体刺激空間へ変換する詳細な技術的プロセスを解説しています。
これにより、対象生物が捕食者にどう見えているかを探ることを目的としています。
【速報記事】FlutterKaigi2025 現地参加レポート
FlutterKaigi 2025の現地参加レポート。
本記事では、OSセキュリティ問題への対応、DevToolsを活用したアプリのパフォーマンス改善、ビルドキャッシュの仕組みと高速化、AI駆動E2Eテストの検証と課題、RenderObjectによる描画の仕組み、Dart ASTの活用、アプリのセキュリティ対策など、最新のFlutter開発における幅広い技術的知見を詳細に共有した。
プラットフォームの課題に迅速に対応するFlutterへの信頼を再確認し、今後の開発への意欲を示す内容となっている。

【速報記事】FlutterKaigi2025 現地参加レポート
FlutterKaigi 2025の現地参加レポート。
本記事では、OSセキュリティ問題への対応、DevToolsを活用したアプリのパフォーマンス改善、ビルドキャッシュの仕組みと高速化、AI駆動E2Eテストの検証と課題、RenderObjectによる描画の仕組み、Dart ASTの活用、アプリのセキュリティ対策など、最新のFlutter開発における幅広い技術的知見を詳細に共有した。
プラットフォームの課題に迅速に対応するFlutterへの信頼を再確認し、今後の開発への意欲を示す内容となっている。
MoonBit 最高 2025
MoonBitは、TypeScriptやRustの課題を解決する静的型関数型言語である。
Rust風の構文、式志向、強力なツールチェイン、そして軽量な生成コードが特徴。
筆者はReactバインディングの実装に成功し、実用レベルに達しつつあると評価している。
一方で、言語仕様はまだ頻繁に変更されており、特に非同期やネイティブバックエンド周りの実装安定性に課題が残るため、公式な安定版リリース(2026年予定)を待つ選択肢も提示されている。

MoonBit 最高 2025
MoonBitは、TypeScriptやRustの課題を解決する静的型関数型言語である。
Rust風の構文、式志向、強力なツールチェイン、そして軽量な生成コードが特徴。
筆者はReactバインディングの実装に成功し、実用レベルに達しつつあると評価している。
一方で、言語仕様はまだ頻繁に変更されており、特に非同期やネイティブバックエンド周りの実装安定性に課題が残るため、公式な安定版リリース(2026年予定)を待つ選択肢も提示されている。
Cursor×MCPでスプレッドシートを使ったPM業務を効率化する環境を構築しよう
この記事は、AI開発環境CursorとGoogleスプレッドシートを連携させ、PM業務を効率化する環境構築手順を解説しています。
Model Context Protocol(MCP)サーバーを利用することで、CursorのAIアシスタントが自然言語の指示に基づき、スプレッドシートのデータを読み書き、操作できるようにします。
具体的な手順として、Google CloudでのAPI有効化、サービスアカウントの作成と連携設定、およびMCP設定ファイルの配置方法が詳細に説明されています。

Cursor×MCPでスプレッドシートを使ったPM業務を効率化する環境を構築しよう
この記事は、AI開発環境CursorとGoogleスプレッドシートを連携させ、PM業務を効率化する環境構築手順を解説しています。
Model Context Protocol(MCP)サーバーを利用することで、CursorのAIアシスタントが自然言語の指示に基づき、スプレッドシートのデータを読み書き、操作できるようにします。
具体的な手順として、Google CloudでのAPI有効化、サービスアカウントの作成と連携設定、およびMCP設定ファイルの配置方法が詳細に説明されています。
AIエージェント機能を継続的に生み出すプロダクトマネジメントについて
LayerXバクラク事業部は、既存の優先事項や組織構造から遅れていたAIエージェント開発を加速するため、ロードマップを半年間白紙化した。
PoCの壁を超えるため、ニーズに基づくユースケースカタログを作成し、エンジニアが技術的な実現性を考慮して優先順位を決めることで、継続的にAI機能を創出する体制を確立した。

AIエージェント機能を継続的に生み出すプロダクトマネジメントについて
LayerXバクラク事業部は、既存の優先事項や組織構造から遅れていたAIエージェント開発を加速するため、ロードマップを半年間白紙化した。
PoCの壁を超えるため、ニーズに基づくユースケースカタログを作成し、エンジニアが技術的な実現性を考慮して優先順位を決めることで、継続的にAI機能を創出する体制を確立した。
JS→TS移行で「型を書くだけ」じゃなかった話 - 型を書いて気づいた5つの設計の甘さ
JavaScriptからTypeScriptへの移行を通じ、単に型を書くだけでは終わらず、既存コードの設計上の甘さ(メモリリーク、レスポンス検証不足、タイムアウト欠如など)が明確になった。
型定義の厳格さが、開発者にイベントハンドラのクリーンアップやランタイム検証、適切なエラー処理といったセキュリティ・堅牢性に関わる問題を認識させ、安全なコード設計へと改善を促す強力なきっかけとなったことをまとめている。

JS→TS移行で「型を書くだけ」じゃなかった話 - 型を書いて気づいた5つの設計の甘さ
JavaScriptからTypeScriptへの移行を通じ、単に型を書くだけでは終わらず、既存コードの設計上の甘さ(メモリリーク、レスポンス検証不足、タイムアウト欠如など)が明確になった。
型定義の厳格さが、開発者にイベントハンドラのクリーンアップやランタイム検証、適切なエラー処理といったセキュリティ・堅牢性に関わる問題を認識させ、安全なコード設計へと改善を促す強力なきっかけとなったことをまとめている。
LLM開発の裏で行われるデバッグ作業: PyTorch DCP
LLMやVLM開発で利用するPyTorchの最新版へのアップデート作業中、PyTorch DCPのチェックポイント読み込み時に必要なメタデータフィールドが存在しない問題が発生しました。
本記事は、スーパーコンピュータ環境でNGC PyTorchコンテナを利用し、この問題を解決するまでの詳細なデバッグ作業と、その過程で検討された原因と解決策を紹介します。

LLM開発の裏で行われるデバッグ作業: PyTorch DCP
LLMやVLM開発で利用するPyTorchの最新版へのアップデート作業中、PyTorch DCPのチェックポイント読み込み時に必要なメタデータフィールドが存在しない問題が発生しました。
本記事は、スーパーコンピュータ環境でNGC PyTorchコンテナを利用し、この問題を解決するまでの詳細なデバッグ作業と、その過程で検討された原因と解決策を紹介します。
Moonbit で React アプリを書く
筆者はMoonbitを実用化するため、JavaScriptバックエンドとFFIを活用し、ReactによるSPA構築を実現しました。
Reactプログラマが自然に扱えるAPIを目指し、DOMやReactなどの外部ライブラリに必要な各種JavaScriptバインディングを自作・公開しています。
これはTypeScriptの言語由来の不安定さやマンネリへの不満から、Moonbitの持つポテンシャルに期待して取り組まれた実装です。
リポジトリも公開され、開発環境のセットアップ詳細も示されています。

Moonbit で React アプリを書く
筆者はMoonbitを実用化するため、JavaScriptバックエンドとFFIを活用し、ReactによるSPA構築を実現しました。
Reactプログラマが自然に扱えるAPIを目指し、DOMやReactなどの外部ライブラリに必要な各種JavaScriptバインディングを自作・公開しています。
これはTypeScriptの言語由来の不安定さやマンネリへの不満から、Moonbitの持つポテンシャルに期待して取り組まれた実装です。
リポジトリも公開され、開発環境のセットアップ詳細も示されています。
わいの生成AIがカスコードばっか出してくるんやが
生成AIを使ったコーディングの品質は、プロンプトの具体性によって劇的に変わります。
抽象的な指示では、セキュリティや保守性に欠けるコードが出力されやすいです。
高品質なコードを得るには、認証やエラー処理、使用技術など、詳細な要件を含めた具体的なプロンプトを与える必要があります。
生成AIは、利用者の実装イメージを素早く具体化するツールであり、エンジニア自身がコードの品質を判断し、適切に修正・改善できる技術的基礎知識が必須です。
生成AI時代こそ、具体的な指示を出せる「考える力」と「学ぶ力」に価値が集中します。
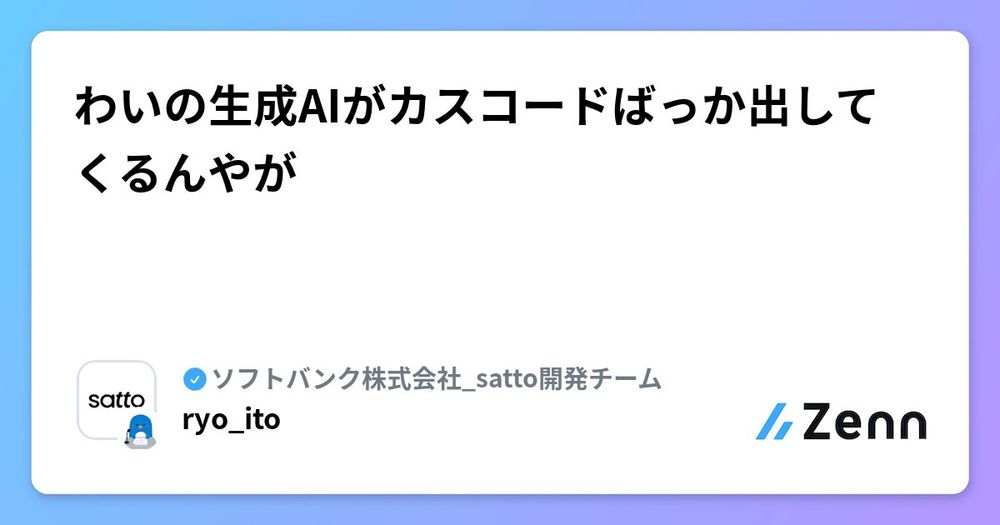
わいの生成AIがカスコードばっか出してくるんやが
生成AIを使ったコーディングの品質は、プロンプトの具体性によって劇的に変わります。
抽象的な指示では、セキュリティや保守性に欠けるコードが出力されやすいです。
高品質なコードを得るには、認証やエラー処理、使用技術など、詳細な要件を含めた具体的なプロンプトを与える必要があります。
生成AIは、利用者の実装イメージを素早く具体化するツールであり、エンジニア自身がコードの品質を判断し、適切に修正・改善できる技術的基礎知識が必須です。
生成AI時代こそ、具体的な指示を出せる「考える力」と「学ぶ力」に価値が集中します。
Flutterアプリ開発のツール管理をFVMからmiseに移行する
IVRyはFlutterアプリ開発におけるツール管理をFVMからmiseに移行した。
miseはFlutter SDKに加え、RubyやCocoaPodsなどの周辺ツールも一元管理できるため、複雑だった環境構築を簡素化し、ローカルとCI環境のバージョン統一を容易にした。
これにより、開発環境のセットアップとメンテナンス性を向上させ、チーム開発の効率化を実現した。

Flutterアプリ開発のツール管理をFVMからmiseに移行する
IVRyはFlutterアプリ開発におけるツール管理をFVMからmiseに移行した。
miseはFlutter SDKに加え、RubyやCocoaPodsなどの周辺ツールも一元管理できるため、複雑だった環境構築を簡素化し、ローカルとCI環境のバージョン統一を容易にした。
これにより、開発環境のセットアップとメンテナンス性を向上させ、チーム開発の効率化を実現した。
【Snowflake】Snowflake IntelligenceにWeb検索機能を統合してみた
企業のデータ分析基盤であるSnowflake Intelligenceに、Web検索APIサービスTavilyを統合する手法を解説しました。
カスタムツールとしてストアドプロシージャを活用することで、社内に蓄積された構造化データとWeb上の非構造化データを組み合わせて分析・洞察を生成できるようになり、データ分析の幅が広がります。

【Snowflake】Snowflake IntelligenceにWeb検索機能を統合してみた
企業のデータ分析基盤であるSnowflake Intelligenceに、Web検索APIサービスTavilyを統合する手法を解説しました。
カスタムツールとしてストアドプロシージャを活用することで、社内に蓄積された構造化データとWeb上の非構造化データを組み合わせて分析・洞察を生成できるようになり、データ分析の幅が広がります。
AIエージェント機能を継続的に生み出すプロダクトマネジメントについて
バクラク事業は、既存機能開発の優先度が高く、LLMを用いたAIエージェント機能の開発が遅延していた。
これを打破するため、プロダクトマネージャー自身がLLM開発を体験し解像度を上げ、トップダウンで半年間のロードマップを白紙化し、AIへの投資に集中した。
開発をPoCで終わらせない仕組みとして、ニーズが証明された「ユースケースカタログ」を作成。
また、技術的な成功確率を高めるため、最終的な機能の優先順位付けと選定はエンジニアに任せることで、AI機能を継続的に生み出す体制を構築した。

AIエージェント機能を継続的に生み出すプロダクトマネジメントについて
バクラク事業は、既存機能開発の優先度が高く、LLMを用いたAIエージェント機能の開発が遅延していた。
これを打破するため、プロダクトマネージャー自身がLLM開発を体験し解像度を上げ、トップダウンで半年間のロードマップを白紙化し、AIへの投資に集中した。
開発をPoCで終わらせない仕組みとして、ニーズが証明された「ユースケースカタログ」を作成。
また、技術的な成功確率を高めるため、最終的な機能の優先順位付けと選定はエンジニアに任せることで、AI機能を継続的に生み出す体制を構築した。
JS→TS移行で「型を書くだけ」じゃなかった話 - 型を書いて気づいた5つの設計の甘さ
JavaScriptからTypeScriptへの移行は、単に型を書く作業ではなく、設計を見直す機会となりました。
型を定義する過程で、JavaScriptコードに潜んでいた「イベントハンドラの削除漏れによるメモリリーク」「APIレスポンスの検証不足」「fetchのタイムアウト欠如」「環境変数のハードコード」「自動再接続時の認証トークン再利用」といった5つの深刻な脆弱性を発見し、コードの安全性と信頼性を大幅に向上させることができました。

JS→TS移行で「型を書くだけ」じゃなかった話 - 型を書いて気づいた5つの設計の甘さ
JavaScriptからTypeScriptへの移行は、単に型を書く作業ではなく、設計を見直す機会となりました。
型を定義する過程で、JavaScriptコードに潜んでいた「イベントハンドラの削除漏れによるメモリリーク」「APIレスポンスの検証不足」「fetchのタイムアウト欠如」「環境変数のハードコード」「自動再接続時の認証トークン再利用」といった5つの深刻な脆弱性を発見し、コードの安全性と信頼性を大幅に向上させることができました。

