
今月はノーベル賞特集に加え、化学賞の受賞テーマであるMOF の最前線を紹介する特集も掲載しています。
人気連載「世界で一番美しいウイルス事件簿」は最終回。ぜひお楽しみに☺︎
ほかにも楽しい記事がそろっておりますので、お手にとっていただければ嬉しいです😌
11月19日発売です。


今月はノーベル賞特集に加え、化学賞の受賞テーマであるMOF の最前線を紹介する特集も掲載しています。
人気連載「世界で一番美しいウイルス事件簿」は最終回。ぜひお楽しみに☺︎
ほかにも楽しい記事がそろっておりますので、お手にとっていただければ嬉しいです😌
11月19日発売です。
国石・ヒスイから見つかった新鉱物「アマテラス石」
ある方向には超伝導状態の電流が、逆方向には通常の電流が流れる「超伝導ダイオード効果」
注目を集める合成薬物「ニタゼン」
など今月も楽しい記事がたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。
本日10月18日発売です☺︎


国石・ヒスイから見つかった新鉱物「アマテラス石」
ある方向には超伝導状態の電流が、逆方向には通常の電流が流れる「超伝導ダイオード効果」
注目を集める合成薬物「ニタゼン」
など今月も楽しい記事がたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。
本日10月18日発売です☺︎
化学者の八木亜樹子先生、天文学者の成田憲保先生へのインタビュー
進展著しい「人工酵素の設計」に関する最新の話題
吉田賢右先生による「私にとって科学とは」
をはじめ、今月も楽しい記事がたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。
本日9月18日発売です☺︎


化学者の八木亜樹子先生、天文学者の成田憲保先生へのインタビュー
進展著しい「人工酵素の設計」に関する最新の話題
吉田賢右先生による「私にとって科学とは」
をはじめ、今月も楽しい記事がたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。
本日9月18日発売です☺︎
本日8月19日発売です☺︎
奥山雄大先生「においから植物の進化を探る」
きのしたちひろさん「イラストで伝える生き物たちの姿」
羽馬哲也先生「アストロケミストリー 星間空間の化学」
をはじめ、今月も楽しい記事がたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。


本日8月19日発売です☺︎
奥山雄大先生「においから植物の進化を探る」
きのしたちひろさん「イラストで伝える生き物たちの姿」
羽馬哲也先生「アストロケミストリー 星間空間の化学」
をはじめ、今月も楽しい記事がたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。

関口仁子先生「原子核を形づくる力、三体核力」
西増弘志先生「タンパク質構造から生命現象に迫る」
竹内淳先生「エントロピーとは何か? 統計力学編」
をはじめ、今月も楽しい記事がたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。
本日7月18日発売です☺︎


関口仁子先生「原子核を形づくる力、三体核力」
西増弘志先生「タンパク質構造から生命現象に迫る」
竹内淳先生「エントロピーとは何か? 統計力学編」
をはじめ、今月も楽しい記事がたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。
本日7月18日発売です☺︎
第7回のテーマは、「変化する機械翻訳の特徴」
機械翻訳は日々進歩しており、訳文の傾向にも変化が見られるようです。
今回はDeepL翻訳とGoogle翻訳を比較しながら、そうした変化をどう捉え、英訳作業にどう活かすのか、各ツールの現時点での特徴とともに紹介してくださいました☺︎

第7回のテーマは、「変化する機械翻訳の特徴」
機械翻訳は日々進歩しており、訳文の傾向にも変化が見られるようです。
今回はDeepL翻訳とGoogle翻訳を比較しながら、そうした変化をどう捉え、英訳作業にどう活かすのか、各ツールの現時点での特徴とともに紹介してくださいました☺︎
特集「量子科学技術の現在地」
量子力学の誕生から100年。
本号では基礎研究にとどまらず多様な展開を見せている「量子科学技術」の今を、7本の記事+コラムで紹介しています。
このほか、大塚淳先生の「科学の物語と統計学」をはじめ楽しい記事が今月もたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。
6月18日発売です☺︎


特集「量子科学技術の現在地」
量子力学の誕生から100年。
本号では基礎研究にとどまらず多様な展開を見せている「量子科学技術」の今を、7本の記事+コラムで紹介しています。
このほか、大塚淳先生の「科学の物語と統計学」をはじめ楽しい記事が今月もたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。
6月18日発売です☺︎
科学者・橘 省吾さんと小説家・伊与原 新さんによる対談「科学と文学」
固体化学者・山本隆文先生へのインタビュー
佐藤健太郎さんによる「化学の世界のギネスブック」
など楽しい記事が今月もたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。
本日5月20日発売です☺︎


科学者・橘 省吾さんと小説家・伊与原 新さんによる対談「科学と文学」
固体化学者・山本隆文先生へのインタビュー
佐藤健太郎さんによる「化学の世界のギネスブック」
など楽しい記事が今月もたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。
本日5月20日発売です☺︎
武田俊太郎先生の「光量子コンピュータ──光をつくり、操り、測定する」
高木里奈先生・関真一郎先生の「電子が織りなす磁性の世界」
甘利俊一先生のエッセイ「私と数理工学」
などの記事をはじめ、楽しい記事がたくさんありますので、ご覧いただけると嬉しいです。
4月18日発売です☺︎


武田俊太郎先生の「光量子コンピュータ──光をつくり、操り、測定する」
高木里奈先生・関真一郎先生の「電子が織りなす磁性の世界」
甘利俊一先生のエッセイ「私と数理工学」
などの記事をはじめ、楽しい記事がたくさんありますので、ご覧いただけると嬉しいです。
4月18日発売です☺︎
特集「進展するAI、加速する科学」
本特集ではデミス・ハサビス博士のインタビューのほか、6名の科学者がAIの活用で変わりつつある科学の最新動向を紹介してくださいました。
新連載は次の2本です。
岡野原大輔先生による「AIによる計算化学の発展」
泉賢太郎先生による「数理の目で見る地学の世界」
そのほか、
島尻拓哉先生、石垣侑祐先生の「What is a bond?」
松浦壮先生の「どうして時間は前に進むのだろう?」
御手洗菜美子先生の「物理と生物の交差点」をはじめ充実した記事がたくさんありますので、お手にとって頂けると嬉しいです☺︎


特集「進展するAI、加速する科学」
本特集ではデミス・ハサビス博士のインタビューのほか、6名の科学者がAIの活用で変わりつつある科学の最新動向を紹介してくださいました。
新連載は次の2本です。
岡野原大輔先生による「AIによる計算化学の発展」
泉賢太郎先生による「数理の目で見る地学の世界」
そのほか、
島尻拓哉先生、石垣侑祐先生の「What is a bond?」
松浦壮先生の「どうして時間は前に進むのだろう?」
御手洗菜美子先生の「物理と生物の交差点」をはじめ充実した記事がたくさんありますので、お手にとって頂けると嬉しいです☺︎
今月はアストロバイオロジーの特集号。関根康人先生、橘省吾先生、中村龍平先生に異なる視点から解説していただきました。
最終回を迎える人気の連載をはじめ、魅力的な記事が沢山ありますのでお手に取っていただけましたらうれしいです☺︎


今月はアストロバイオロジーの特集号。関根康人先生、橘省吾先生、中村龍平先生に異なる視点から解説していただきました。
最終回を迎える人気の連載をはじめ、魅力的な記事が沢山ありますのでお手に取っていただけましたらうれしいです☺︎
今月のテーマは「食べるコーヒー」
もともとは飲み物だったチョコレート。コーヒー、茶とともに広く愛飲されるようになったのに、どうしてチョコレートだけが固形の食品になったのか。
また、それなら食べるコーヒーはないの?という話まで紹介していただきました☺︎
記事中に登場するヨインドYOINEDは、見た目はチョコレートなのに味はしっかりコーヒー!まさに「食べるコーヒー」で、美味しく楽しくいだだきました。


今月のテーマは「食べるコーヒー」
もともとは飲み物だったチョコレート。コーヒー、茶とともに広く愛飲されるようになったのに、どうしてチョコレートだけが固形の食品になったのか。
また、それなら食べるコーヒーはないの?という話まで紹介していただきました☺︎
記事中に登場するヨインドYOINEDは、見た目はチョコレートなのに味はしっかりコーヒー!まさに「食べるコーヒー」で、美味しく楽しくいだだきました。
田中一義『化学への数学──基本の10章』
化学に登場する数学を、独学でも読み進められるよう丁寧に、そして例題を豊富に解説しています。
特に物理化学の教科書に登場する数式で悩んでいる方にはおすすめの一冊です☺︎
www.tkd-pbl.com/book/b101099...

田中一義『化学への数学──基本の10章』
化学に登場する数学を、独学でも読み進められるよう丁寧に、そして例題を豊富に解説しています。
特に物理化学の教科書に登場する数式で悩んでいる方にはおすすめの一冊です☺︎
www.tkd-pbl.com/book/b101099...
特集「ロスト・セオリー 絶滅した思想」
「古生物図鑑を眺めるのが楽しいように、絶滅した学説や思想を集めて一望してみると意外な楽しさがありそうです」と。
とても面白いテーマで、「周期表には載っていない元素名」も当てはまるな等と思いながら、楽しく読んでいるのだった☺︎

特集「ロスト・セオリー 絶滅した思想」
「古生物図鑑を眺めるのが楽しいように、絶滅した学説や思想を集めて一望してみると意外な楽しさがありそうです」と。
とても面白いテーマで、「周期表には載っていない元素名」も当てはまるな等と思いながら、楽しく読んでいるのだった☺︎
今月のテーマは「2050年問題」
2050年までに気候変動の影響でコーヒーの栽培適地が半減するという予測「2050年問題」について、そのきっかけとなった記事の内容をはじめ、コーヒーを取り巻く問題は気候変動だけではない…という点について紹介していただきました☺︎

今月のテーマは「2050年問題」
2050年までに気候変動の影響でコーヒーの栽培適地が半減するという予測「2050年問題」について、そのきっかけとなった記事の内容をはじめ、コーヒーを取り巻く問題は気候変動だけではない…という点について紹介していただきました☺︎
スペースの都合で入れることができなかったのですが、特集記事はほかにもたくさんあります☺︎

スペースの都合で入れることができなかったのですが、特集記事はほかにもたくさんあります☺︎
特集「量子力学2025──誕生から100年、拡大するその科学」
2025年は量子力学の誕生から100年。本号ではこの100年を振返りながら、量子科学の現在を17の解説とコラムで紹介しています。
新連載をはじめ他にも充実した記事が沢山ありますので、お手にとって頂けると嬉しいです。
新連載は次の3本です☺︎
畠山哲央先生によるエッセイ「in cephalo biologyの散歩道」
田中一義先生の「基礎から学ぶ物理化学」
中山裕木子先生の「時代のツールを活用した科学技術英語ライティング術」


特集「量子力学2025──誕生から100年、拡大するその科学」
2025年は量子力学の誕生から100年。本号ではこの100年を振返りながら、量子科学の現在を17の解説とコラムで紹介しています。
新連載をはじめ他にも充実した記事が沢山ありますので、お手にとって頂けると嬉しいです。
新連載は次の3本です☺︎
畠山哲央先生によるエッセイ「in cephalo biologyの散歩道」
田中一義先生の「基礎から学ぶ物理化学」
中山裕木子先生の「時代のツールを活用した科学技術英語ライティング術」
第9回「化学のための量子コンピュータ入門」のテーマは「量子コンピュータと量子化学」。
量子コンピュータの活躍が特に期待される量子化学計算。今回はその基礎から量子コンピュータとの関係、そして今後の展望まで、水上 渉先生がわかりやすく紹介してくださっています☺︎
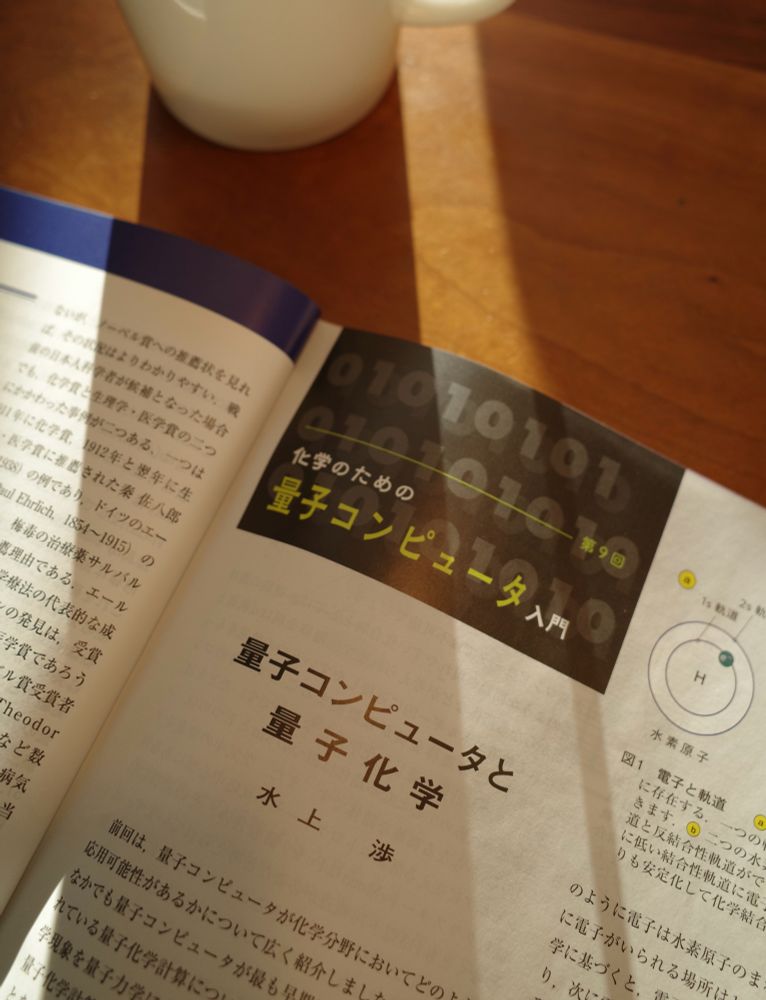
第9回「化学のための量子コンピュータ入門」のテーマは「量子コンピュータと量子化学」。
量子コンピュータの活躍が特に期待される量子化学計算。今回はその基礎から量子コンピュータとの関係、そして今後の展望まで、水上 渉先生がわかりやすく紹介してくださっています☺︎
今月のテーマは「コーヒー×アルコール」。
ブランデーを使った「カフェ・ロワイヤル」や、アイリッシュウイスキーを使った「アイリッシュ・コーヒー」など、寒い時期にぴったりのお酒を使ったコーヒーを紹介していただきました。
この冬に色々と試してみたいです☺︎

今月のテーマは「コーヒー×アルコール」。
ブランデーを使った「カフェ・ロワイヤル」や、アイリッシュウイスキーを使った「アイリッシュ・コーヒー」など、寒い時期にぴったりのお酒を使ったコーヒーを紹介していただきました。
この冬に色々と試してみたいです☺︎
福島竜輝 著『授業では教えてくれない微積分学』

福島竜輝 著『授業では教えてくれない微積分学』
江頭和宏さんの「周期表には載っていない元素名」では、周期表に載っているタリウムthalliumではなく、l(エル)が一つ足りない「タリウムthalium」について紹介していただきました☺︎
さらには、硫黄の綴りにまつわる話なども。

江頭和宏さんの「周期表には載っていない元素名」では、周期表に載っているタリウムthalliumではなく、l(エル)が一つ足りない「タリウムthalium」について紹介していただきました☺︎
さらには、硫黄の綴りにまつわる話なども。
今月はノーベル賞の特集号。科学におけるAIの存在感が改めて注目された今年の自然科学分野のノーベル賞について、背景から丁寧に紹介していただきました。
特集以外も楽しく充実した記事がたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。発売中です☺︎

今月はノーベル賞の特集号。科学におけるAIの存在感が改めて注目された今年の自然科学分野のノーベル賞について、背景から丁寧に紹介していただきました。
特集以外も楽しく充実した記事がたくさんありますので、お手にとっていただけると嬉しいです。発売中です☺︎
岡野八代、『ケアの倫理──フェミニズムの政治思想』
「ケアの倫理をフェミニズム思想の歴史のなかで文脈化すると同時に、ケアの倫理の嚆矢とされる『もうひとつの声で』をフェミニズムの理論と運動の歴史に位置づけ直すことも目的とする」と。

岡野八代、『ケアの倫理──フェミニズムの政治思想』
「ケアの倫理をフェミニズム思想の歴史のなかで文脈化すると同時に、ケアの倫理の嚆矢とされる『もうひとつの声で』をフェミニズムの理論と運動の歴史に位置づけ直すことも目的とする」と。


