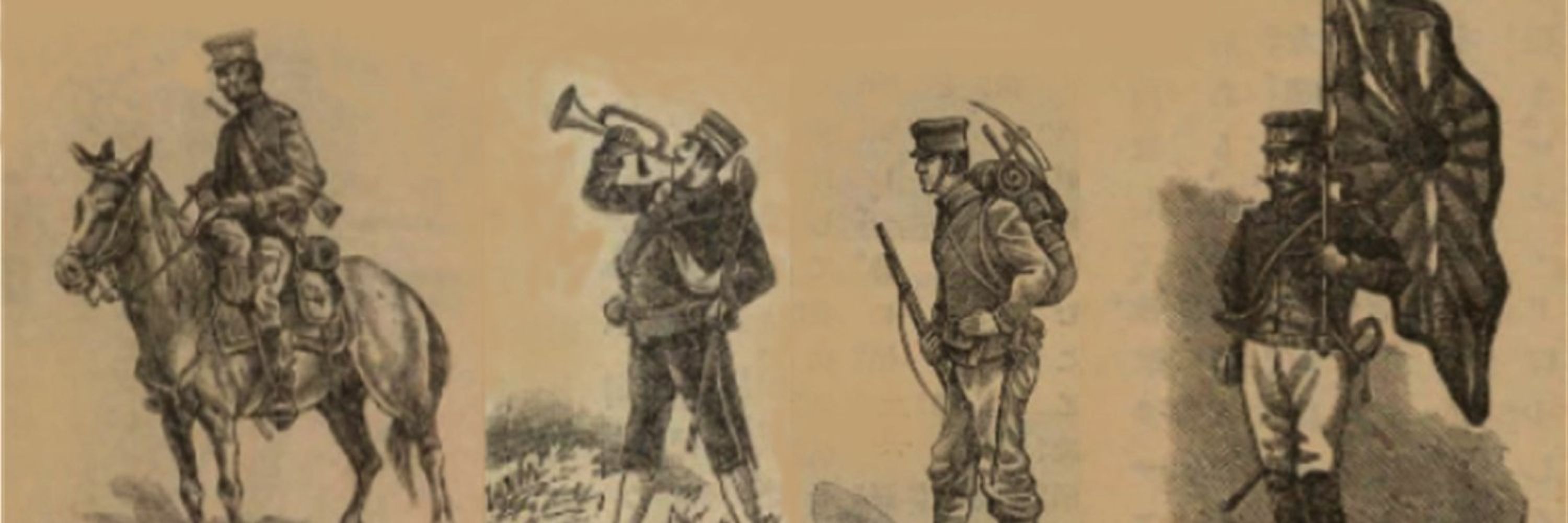
歴史(経済史・軍事史・流通史・思想史)など論及
お気に入りの本などの感想も時々書いてみる
チェスタトン 安西徹雄訳

チェスタトン 安西徹雄訳
『メディアコントロールー日本の戦争報道』前坂俊之,旬報社,2005

『メディアコントロールー日本の戦争報道』前坂俊之,旬報社,2005

フィリピンの闘士リカルテ将軍とラウレル大統領の評伝。リカルテ将軍はスペイン及びアメリカからの独立闘争、ラウレル大統領はアメリカからの独立闘争を経て、共通の敵を持つ日本と協力関係になる。対日協力者として評価も分かれるが歴史の一面として知っておきたいところ。
『フィリピンの独立と日本ーリカルテ将軍とラウレル大統領』寺見元恵,彩流社,2014
なお本書は「15歳からの『伝記で知るアジアの近現代史』シリーズ」と銘打ち、「ですます調」で非常に分かり易い。対日協力者という先入観を一旦置いて、フィリピンの独立運動の一面を分かり易く知る事ができる。

フィリピンの闘士リカルテ将軍とラウレル大統領の評伝。リカルテ将軍はスペイン及びアメリカからの独立闘争、ラウレル大統領はアメリカからの独立闘争を経て、共通の敵を持つ日本と協力関係になる。対日協力者として評価も分かれるが歴史の一面として知っておきたいところ。
『フィリピンの独立と日本ーリカルテ将軍とラウレル大統領』寺見元恵,彩流社,2014
なお本書は「15歳からの『伝記で知るアジアの近現代史』シリーズ」と銘打ち、「ですます調」で非常に分かり易い。対日協力者という先入観を一旦置いて、フィリピンの独立運動の一面を分かり易く知る事ができる。
『「やらせ」の政治経済学ー発見から破綻まで』後藤玲子,玉井雅隆,宮脇昇編,ミネルヴァ書房,2017

『「やらせ」の政治経済学ー発見から破綻まで』後藤玲子,玉井雅隆,宮脇昇編,ミネルヴァ書房,2017
『日清戦争の研究』中塚明,青木書店,1968

『日清戦争の研究』中塚明,青木書店,1968
「日本が破滅へ向かう戦争の第一歩となった満洲事変は、機密費がぎりぎりにまで削り込まれた段階で企てられていた。ところが、いったん戦争が始まると状況は一変し、あり余る機密費がもたらされ、危機が拡大、長期化するにつれ軍人を潤す余禄は増えていった」
『軍事機密費―GHQ特命捜査ファイル』渡辺延志,岩波書店,2018

「日本が破滅へ向かう戦争の第一歩となった満洲事変は、機密費がぎりぎりにまで削り込まれた段階で企てられていた。ところが、いったん戦争が始まると状況は一変し、あり余る機密費がもたらされ、危機が拡大、長期化するにつれ軍人を潤す余禄は増えていった」
『軍事機密費―GHQ特命捜査ファイル』渡辺延志,岩波書店,2018
『歩兵第百十四聯隊(高知) 通信中隊誌』
中隊編制・組織表


『歩兵第百十四聯隊(高知) 通信中隊誌』
中隊編制・組織表
『思想史講義―明治篇Ⅱ』山口輝臣,福家崇洋 編,筑摩書房,2023
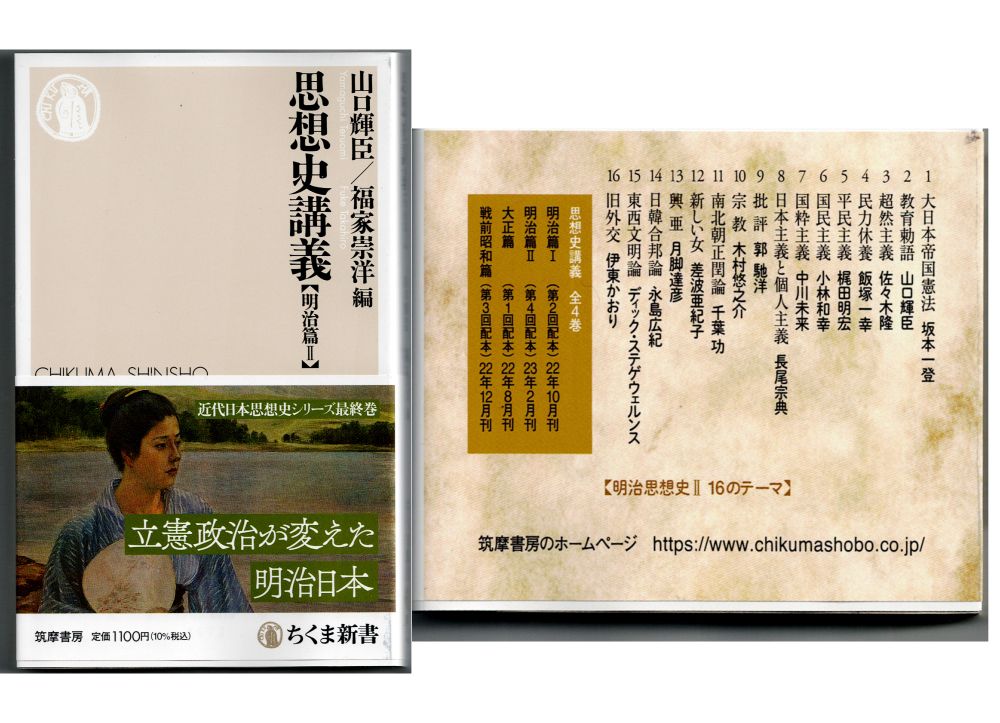
『思想史講義―明治篇Ⅱ』山口輝臣,福家崇洋 編,筑摩書房,2023
天皇退位計画・カトリック改宗説・資産隠匿疑惑などなど
『英国機密ファイルの昭和天皇』徳本栄一郎,新潮社,2007

天皇退位計画・カトリック改宗説・資産隠匿疑惑などなど
『英国機密ファイルの昭和天皇』徳本栄一郎,新潮社,2007
田島道治の『昭和天皇拝謁記全7巻』をもとに戦中から「戦後」の昭和帝の言動を分析する。『拝謁記』全部を読む時間も余裕もない人はこれを読んでみるといいかもしれない。
『昭和天皇の戦争認識』山田朗,新日本出版社,2023

田島道治の『昭和天皇拝謁記全7巻』をもとに戦中から「戦後」の昭和帝の言動を分析する。『拝謁記』全部を読む時間も余裕もない人はこれを読んでみるといいかもしれない。
『昭和天皇の戦争認識』山田朗,新日本出版社,2023
教材編には通信兵操典・通信教範・無線外史が所収。
隊史編には明治建軍以来の通信隊の歴史が所収 。
戦史編には「支那事変(日中戦争)」の第一軍と通信隊の記録が所収。
『万里一条鉄 ―教材編 陸軍通信隊の花伝書』1985
〃―隊史編
〃―戦史編

教材編には通信兵操典・通信教範・無線外史が所収。
隊史編には明治建軍以来の通信隊の歴史が所収 。
戦史編には「支那事変(日中戦争)」の第一軍と通信隊の記録が所収。
『万里一条鉄 ―教材編 陸軍通信隊の花伝書』1985
〃―隊史編
〃―戦史編
法の恣意的運用や、拡大解釈、改正などによって、人々を縛っていく「治安維持法」。過去の歴史に学んでみよう。
『治安維持法小史』 奥平康弘 岩波書店 2006

法の恣意的運用や、拡大解釈、改正などによって、人々を縛っていく「治安維持法」。過去の歴史に学んでみよう。
『治安維持法小史』 奥平康弘 岩波書店 2006
「倉富日記」は憲政資料室に保管されているが、判読が難解で物量も多く原史料を読み解くのはかなり難しいらしい。本書は重要事件を中心に読解、まとめたもの。
宮中某重大事件・朝鮮王族・柳原白蓮 他
「人の噂話をこよなく愛してすべて聞きとり、それを書かずにはいられなかった日記」倉富日記
>>なんという迷惑で面白い日記だ(*'▽')
『枢密院議長の日記』佐野眞一,講談社,2007

「倉富日記」は憲政資料室に保管されているが、判読が難解で物量も多く原史料を読み解くのはかなり難しいらしい。本書は重要事件を中心に読解、まとめたもの。
宮中某重大事件・朝鮮王族・柳原白蓮 他
「人の噂話をこよなく愛してすべて聞きとり、それを書かずにはいられなかった日記」倉富日記
>>なんという迷惑で面白い日記だ(*'▽')
『枢密院議長の日記』佐野眞一,講談社,2007
『シリーズ 戦争の経験を問う 抵抗と協力のはざま―近代ビルマ史のなかのイギリスと日本』 根本敬 岩波書店,2010
「抵抗」か「協力」かではとらえきれない、植民地期ビルマの現実。いま論じ直される近代ビルマ史。日本軍が軍政を敷く以前のビルマの対イギリス独立運動など知ることができます。

『シリーズ 戦争の経験を問う 抵抗と協力のはざま―近代ビルマ史のなかのイギリスと日本』 根本敬 岩波書店,2010
「抵抗」か「協力」かではとらえきれない、植民地期ビルマの現実。いま論じ直される近代ビルマ史。日本軍が軍政を敷く以前のビルマの対イギリス独立運動など知ることができます。
『さらばラバウル―最後の二百二十九聯隊』大島義郎,1967
でも死んだら意味ないわな。 将校は稼げるからいいが、付き合わされる兵隊はたまったもんではない
戦後、講和条約締結後に元職業軍人への恩給が復活となったわけですが、その際も戦前の月給と同じように階級が上がるほど手厚かったわけです。一般兵士は雀の涙ですが。この恩給絡みが保守系政党の票田とな…(皆まで言うな

『さらばラバウル―最後の二百二十九聯隊』大島義郎,1967
でも死んだら意味ないわな。 将校は稼げるからいいが、付き合わされる兵隊はたまったもんではない
戦後、講和条約締結後に元職業軍人への恩給が復活となったわけですが、その際も戦前の月給と同じように階級が上がるほど手厚かったわけです。一般兵士は雀の涙ですが。この恩給絡みが保守系政党の票田とな…(皆まで言うな
答 「日本関東軍司令官は逮捕者の中に日本軍の政策の実施に害を及ぼす者がいる場合、その場で殺せと指示しました。この指示に従って逮捕者を殺害しました」
問 「『厳重処分』とは、意のままに殺せるということですか?」
答 「はい。関東軍司令官の承認を得て殺害しました」
問 「作戦で捕らえられたのは兵士ですか?それとも庶民ですか?」
答 「中国の抗日兵士、民間人の中国人もいました」
『満洲国の治安維持法』荻野富士夫六花出版

答 「日本関東軍司令官は逮捕者の中に日本軍の政策の実施に害を及ぼす者がいる場合、その場で殺せと指示しました。この指示に従って逮捕者を殺害しました」
問 「『厳重処分』とは、意のままに殺せるということですか?」
答 「はい。関東軍司令官の承認を得て殺害しました」
問 「作戦で捕らえられたのは兵士ですか?それとも庶民ですか?」
答 「中国の抗日兵士、民間人の中国人もいました」
『満洲国の治安維持法』荻野富士夫六花出版
『朝鮮人戦時労働動員』山田昭次,古庄正,樋口雄一,岩波書店,2005

『朝鮮人戦時労働動員』山田昭次,古庄正,樋口雄一,岩波書店,2005
『労働力動員と強制連行《日本史リブレット》099』 西成田豊 山川出版社 2009年

『労働力動員と強制連行《日本史リブレット》099』 西成田豊 山川出版社 2009年
ソ連軍の北方四島への上陸は、千島列島経由ではなく、樺太経由だったことが分かる。占守島の戦闘を等閑視するわけではないが、占守島でソ連軍を食い止めた訳ではない。日付が重要だ。
9月2日には東京湾上の米戦艦ミズーリ号の甲板で降伏文書の調印式があったが、北方四島の一部は調印後に占拠されている点に注意しよう。つまり正式に戦闘が終わっているはずにもかかわらず、ソ連は北方四島の一部を武力占拠しているわけだ。
『日ソ戦争への道-ノモンハンから千島占領まで』 ボリス・スラヴィンスキー著 加藤幸廣訳,1999

ソ連軍の北方四島への上陸は、千島列島経由ではなく、樺太経由だったことが分かる。占守島の戦闘を等閑視するわけではないが、占守島でソ連軍を食い止めた訳ではない。日付が重要だ。
9月2日には東京湾上の米戦艦ミズーリ号の甲板で降伏文書の調印式があったが、北方四島の一部は調印後に占拠されている点に注意しよう。つまり正式に戦闘が終わっているはずにもかかわらず、ソ連は北方四島の一部を武力占拠しているわけだ。
『日ソ戦争への道-ノモンハンから千島占領まで』 ボリス・スラヴィンスキー著 加藤幸廣訳,1999

