
レコード・CD・カセットテープなど
web🛸
https://monumental-movement.jp
メルカリ🛸
https://jp.mercari.com/user/profile/937430248?afid=6142608987
"For those living outside of Japan, you can safely make purchases on Mercari through Buyee or Doorzo"
#DanceRajaDance
#MMRコラム
80年代末、インド南部の都市文化がディスコと共に爆発した。Vijaya Anandの『Dance Raja Dance』は、Karnataka州が生んだ音と映像のカーニバル....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-dance...
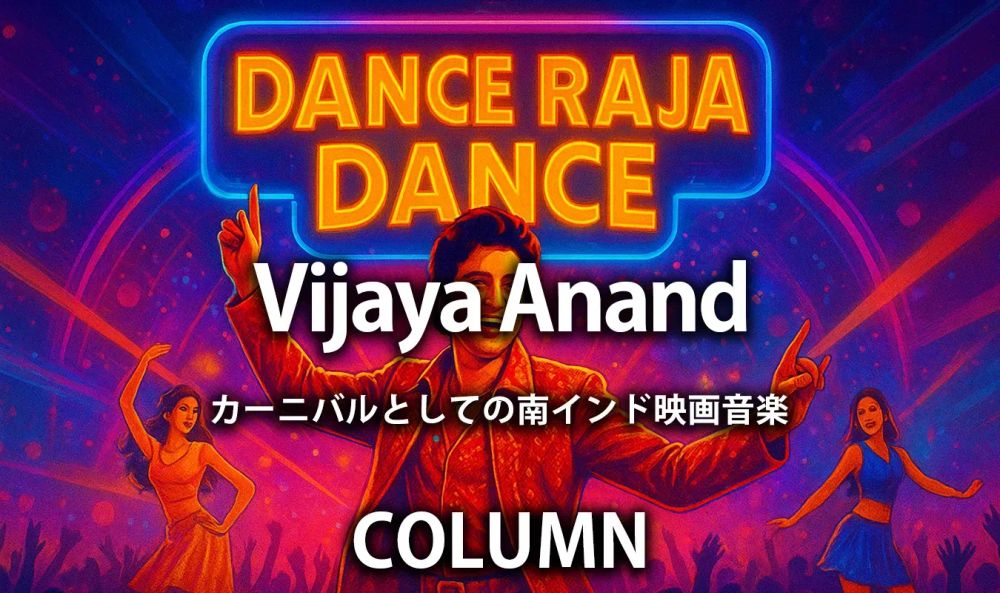
#DanceRajaDance
#MMRコラム
80年代末、インド南部の都市文化がディスコと共に爆発した。Vijaya Anandの『Dance Raja Dance』は、Karnataka州が生んだ音と映像のカーニバル....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-dance...
#MMRコラム
1950年代のアメリカ。
テレビが家庭に普及し、冷戦と繁栄が同居する時代、エキゾチカと呼ばれる音楽が登場
ティキ文化、ハワイアン・バー、ルンバのリズム、そして異国風のメロディ
その中心には、ミステリアスな鍵盤奏者「コルラ・パンディット」の姿が...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-korla...

#MMRコラム
1950年代のアメリカ。
テレビが家庭に普及し、冷戦と繁栄が同居する時代、エキゾチカと呼ばれる音楽が登場
ティキ文化、ハワイアン・バー、ルンバのリズム、そして異国風のメロディ
その中心には、ミステリアスな鍵盤奏者「コルラ・パンディット」の姿が...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-korla...
#MFSB
#MMRコラム
1970年代初頭、アメリカ東海岸の都市・フィラデルフィアで、後に「ディスコ」の原型となる音楽革命が起きた。
その中心にいたのが、「MFSB」と「Salsoul Orchestra」で....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-salsoul

#MFSB
#MMRコラム
1970年代初頭、アメリカ東海岸の都市・フィラデルフィアで、後に「ディスコ」の原型となる音楽革命が起きた。
その中心にいたのが、「MFSB」と「Salsoul Orchestra」で....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-salsoul
(岩波書店、2017年)
芸能山城組主宰・山城祥二(大橋力)が長年にわたり研究してきた「超高周波音」の生理的・心理的効果をまとめた科学的著作。人間の聴覚では感知できない高周波成分(ハイパーソニック)が、脳波活動や快感、集中力に影響を与えることを実験的に示し、音楽や環境音の新たな意義を提示。芸能山城組の音響実践の裏づけともなる理論書であり、音を「感じる」身体と文明の関係を科学と芸術の両面から探究する一冊。
amzn.to/3WPuS9o
(岩波書店、2017年)
芸能山城組主宰・山城祥二(大橋力)が長年にわたり研究してきた「超高周波音」の生理的・心理的効果をまとめた科学的著作。人間の聴覚では感知できない高周波成分(ハイパーソニック)が、脳波活動や快感、集中力に影響を与えることを実験的に示し、音楽や環境音の新たな意義を提示。芸能山城組の音響実践の裏づけともなる理論書であり、音を「感じる」身体と文明の関係を科学と芸術の両面から探究する一冊。
amzn.to/3WPuS9o
#奄美大島
#MMRコラム
貯蔵庫の奥からクラシック、ジャズ、島唄が微かに流れ、ステンレスタンクの内側でアルコール分子が震える
彼らは言う——「音が焼酎をやわらかくする」...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-shoch...

#奄美大島
#MMRコラム
貯蔵庫の奥からクラシック、ジャズ、島唄が微かに流れ、ステンレスタンクの内側でアルコール分子が震える
彼らは言う——「音が焼酎をやわらかくする」...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-shoch...
#Akira
#MMRコラム
芸能山城組は1970年代後半から1980年代に「世界80系統に及ぶ民族パフォーマンス」を実際に演奏・研究
それは単なる民族音楽の収集ではなく、「人間が群れとして発する音とは何か」という根源的問いへの探求で...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-yamas...

#Akira
#MMRコラム
芸能山城組は1970年代後半から1980年代に「世界80系統に及ぶ民族パフォーマンス」を実際に演奏・研究
それは単なる民族音楽の収集ではなく、「人間が群れとして発する音とは何か」という根源的問いへの探求で...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-yamas...
#MMRコラム
1979年、『機動戦士ガンダム』は単なるロボットアニメではなく、 戦争と人間を描くリアリズム作品として誕生した。 その背後で鳴り響いていたのは、渡辺岳夫によるオーケストラ的スコアと...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-gundam

#MMRコラム
1979年、『機動戦士ガンダム』は単なるロボットアニメではなく、 戦争と人間を描くリアリズム作品として誕生した。 その背後で鳴り響いていたのは、渡辺岳夫によるオーケストラ的スコアと...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-gundam
#DubTechno
#MMRコラム
1993年、「Basic Channel」名義で数枚の12インチをリリース
ジャケットには情報がほとんど記載されず、ただ無機質なエンボス・ロゴだけ
それは「匿名性」をブランド化する最初の試み...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-basic...

#DubTechno
#MMRコラム
1993年、「Basic Channel」名義で数枚の12インチをリリース
ジャケットには情報がほとんど記載されず、ただ無機質なエンボス・ロゴだけ
それは「匿名性」をブランド化する最初の試み...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-basic...
#MMRコラム
ダブの本質は、単にエフェクトをかけることではない。
音を削ることによって、新しい空間を生むことにある。
それは、欠落の美学であり、再生産の思想...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-dub-u...

#MMRコラム
ダブの本質は、単にエフェクトをかけることではない。
音を削ることによって、新しい空間を生むことにある。
それは、欠落の美学であり、再生産の思想...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-dub-u...
#tajmahalitravelers
#MMRコラム
1971年、タージ・マハル旅行団はヨーロッパ公演を目的に出発する。
彼らの旅は、単なるツアーではなく「音の巡礼」であった。
電源もステージもない野外で、風・水・群衆・電波と即興的に共鳴する演奏を展開...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-taj-m...

#tajmahalitravelers
#MMRコラム
1971年、タージ・マハル旅行団はヨーロッパ公演を目的に出発する。
彼らの旅は、単なるツアーではなく「音の巡礼」であった。
電源もステージもない野外で、風・水・群衆・電波と即興的に共鳴する演奏を展開...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-taj-m...
#70s
#MMRコラム
1970年代の日本。
夜の街は「ディスコ」の空気を彩ったのは、光るミラーボール、Soul Train的なグルーヴ、そして赤ラークの赤いパッケージだった...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-1970s...

#70s
#MMRコラム
1970年代の日本。
夜の街は「ディスコ」の空気を彩ったのは、光るミラーボール、Soul Train的なグルーヴ、そして赤ラークの赤いパッケージだった...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-1970s...
1983年のマーヴィン・ゲイのインタビュー
youtu.be/L63XR2hFgpg
1983年のマーヴィン・ゲイのインタビュー
youtu.be/L63XR2hFgpg
#ソウルミュージック
#MMRコラム
1982年、ブリュッセルのホテルの一室。 Roland TR-808の乾いたビートが鳴り響く中、Marvin Gayeは孤独にマイクへ向かっていた。 『Midnight Love』—— それは、亡命と再生、愛と自己破壊の狭間で生まれた祈りのアルバム...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-marvi...

#ソウルミュージック
#MMRコラム
1982年、ブリュッセルのホテルの一室。 Roland TR-808の乾いたビートが鳴り響く中、Marvin Gayeは孤独にマイクへ向かっていた。 『Midnight Love』—— それは、亡命と再生、愛と自己破壊の狭間で生まれた祈りのアルバム...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-marvi...
#スタジオジブリ
#MMRコラム
Quincy(クインシー)→ 日本語的発音「クインシー(kuinshi)」をもじり、「久石(ひさいし)」を当てたものとされ、「ジョーンズ(Jones)」の「ジョー」から “Joe” を取って、英語表記「Joe Hisaishi」 ....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-hisai...

#スタジオジブリ
#MMRコラム
Quincy(クインシー)→ 日本語的発音「クインシー(kuinshi)」をもじり、「久石(ひさいし)」を当てたものとされ、「ジョーンズ(Jones)」の「ジョー」から “Joe” を取って、英語表記「Joe Hisaishi」 ....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-hisai...
#MMRコラム
「あの伝説の機材(Roland TB‑303、Roland TR‑808、Roland TR‑909)を、手元のパソコンで使えるようにする」という可能性で....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-rebir...

#MMRコラム
「あの伝説の機材(Roland TB‑303、Roland TR‑808、Roland TR‑909)を、手元のパソコンで使えるようにする」という可能性で....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-rebir...
#MMRコラム
「X JAPAN」「BABYMETAL」「Perfume」「Dir en grey」――
これらの名前を挙げたとき、多くの海外リスナーは熱狂的な記憶とともに彼らを語る。
かつて“ガラパゴス文化”と見なされた....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-visua...

#MMRコラム
「X JAPAN」「BABYMETAL」「Perfume」「Dir en grey」――
これらの名前を挙げたとき、多くの海外リスナーは熱狂的な記憶とともに彼らを語る。
かつて“ガラパゴス文化”と見なされた....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-visua...
#MMRコラム
1997年頃に登場したィンランドの開発者 Oskari Tammelin による「Jeskola Buzz」 はWindows 用のフリーウェア モジュラー・トラッカー/シーケンサーとして、多数のユーザーに支持され...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-jesko...

#MMRコラム
1997年頃に登場したィンランドの開発者 Oskari Tammelin による「Jeskola Buzz」 はWindows 用のフリーウェア モジュラー・トラッカー/シーケンサーとして、多数のユーザーに支持され...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-jesko...
#MMRコラム
1980年代の終わり、日本の音楽界では「シティポップ」という言葉が一度その役割を終えたはずだった。だが2020年代に入って、このジャンルは世界のストリーミングチャートを賑わせ...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-citypop

#MMRコラム
1980年代の終わり、日本の音楽界では「シティポップ」という言葉が一度その役割を終えたはずだった。だが2020年代に入って、このジャンルは世界のストリーミングチャートを賑わせ...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-citypop
#MMRコラム
サンプリングとは、音楽史の中で「引用」と「再構築」を最も直接的に体現する技術だ。70年代後半のヒップホップ黎明期から今日のエレクトロニカまで、ひとつの ドラムブレイク、ベースライン、叫び声が何百、何千もの曲に生まれ変わってきた.....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-sampl...

#MMRコラム
サンプリングとは、音楽史の中で「引用」と「再構築」を最も直接的に体現する技術だ。70年代後半のヒップホップ黎明期から今日のエレクトロニカまで、ひとつの ドラムブレイク、ベースライン、叫び声が何百、何千もの曲に生まれ変わってきた.....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-sampl...
#MMRコラム
1973年に登場した Buchla Music Easel は、アナログ・モジュラーの名機 Buchla 200シリーズ をポータブル化したモデル。
設計者 Don Buchla は、この楽器を「携帯できる作曲環境」と呼んだ。
それは単なる小型モジュラーではなく、“個人の即興装置” として構想された...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-buchl...

#MMRコラム
1973年に登場した Buchla Music Easel は、アナログ・モジュラーの名機 Buchla 200シリーズ をポータブル化したモデル。
設計者 Don Buchla は、この楽器を「携帯できる作曲環境」と呼んだ。
それは単なる小型モジュラーではなく、“個人の即興装置” として構想された...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-buchl...
#EnergyDome
#MMRコラム
DEVOは音楽だけでなく視覚的アイコンをもって新時代のポップアートを体現
その象徴が、彼らがステージやPVで着用した赤いプラスチック製の帽子──エナジードームで...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-devo-...

#EnergyDome
#MMRコラム
DEVOは音楽だけでなく視覚的アイコンをもって新時代のポップアートを体現
その象徴が、彼らがステージやPVで着用した赤いプラスチック製の帽子──エナジードームで...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-devo-...
#MilesDavis
#MMRコラム
1960年代末、マイルス・デイビスの音楽はライブの延長線ではなく、録音編集によって構築された“音の建築物”へと変貌していった。その変革の背後には Teo Maceroの存在が...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-macer...

#MilesDavis
#MMRコラム
1960年代末、マイルス・デイビスの音楽はライブの延長線ではなく、録音編集によって構築された“音の建築物”へと変貌していった。その変革の背後には Teo Maceroの存在が...
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-macer...
#MMRコラム
ラジオから流れる柔らかな旋律。そこに鳴っていたのは、Three Suns ―― アコーディオン、ギター、エレクトリック・オルガンという編成で構築された、1940年代アメリカの家庭音楽の象徴....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-three...

#MMRコラム
ラジオから流れる柔らかな旋律。そこに鳴っていたのは、Three Suns ―― アコーディオン、ギター、エレクトリック・オルガンという編成で構築された、1940年代アメリカの家庭音楽の象徴....
続きはこちらから🔽
monumental-movement.jp/column-three...

